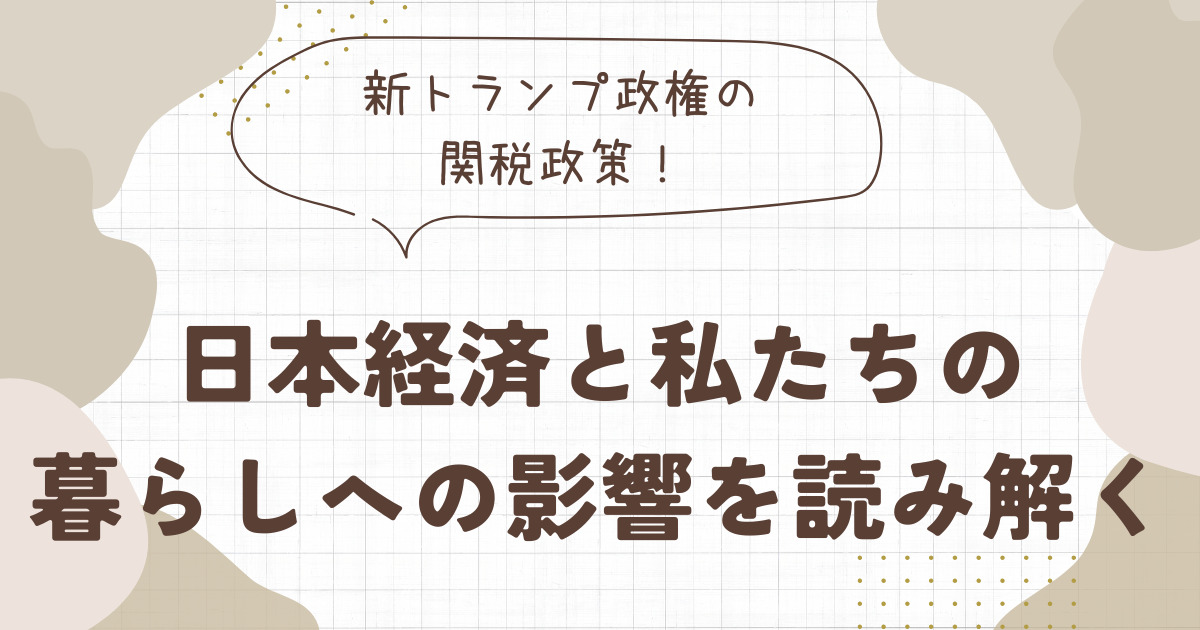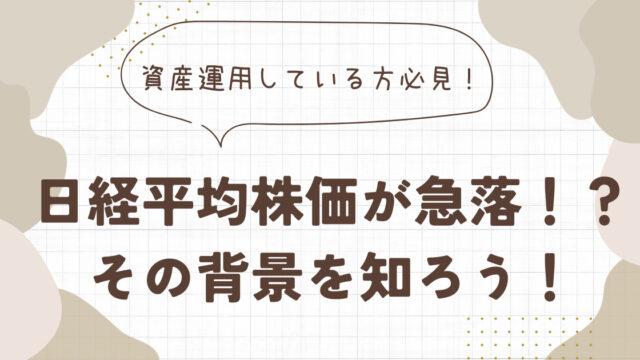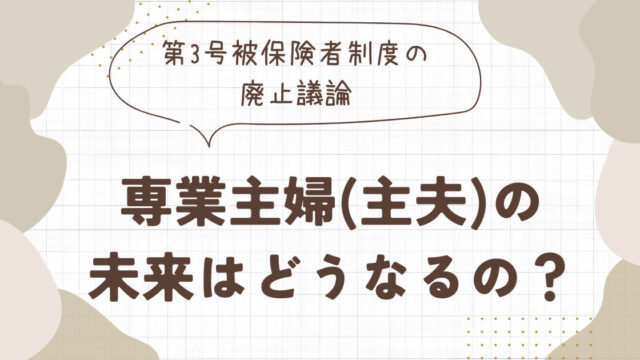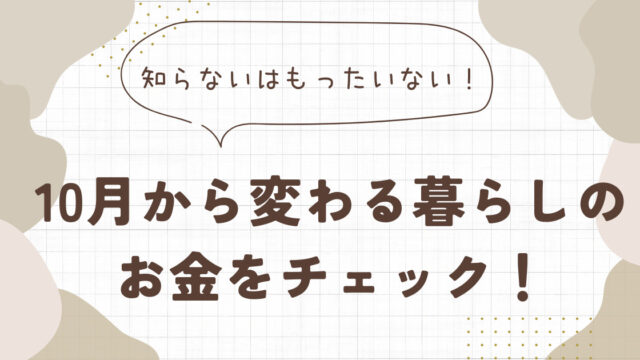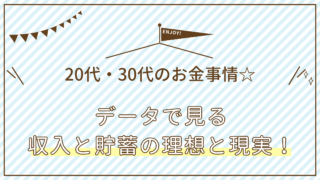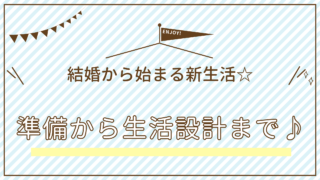みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
2025年1月、トランプ大統領が再び米国のトップに返り咲きました。就任後わずか数ヶ月で、すでに世界経済に大きな変化をもたらす政策が次々と発表されています。特に目立つのが「関税」の話ですね…
「関税って何?」と思う方もいるかもしれませんね。
簡単に言うと、外国から輸入される商品にかける税金のことです。この税金が高くなると、輸入品の価格が上がり、国内産業を守る効果がある一方で、消費者の負担も増えるという両面があります。
トランプ大統領は前政権時代から「アメリカ・ファースト」を掲げ、自国の産業や雇用を守るために積極的に関税を活用してきました。新政権でもこの姿勢は変わらず、むしろさらに強化されている印象です。
今回は、このトランプ政権の関税政策が日本や私たちの暮らしにどう影響するのか、わかりやすくまとめてみました!
トランプ新政権の関税政策の概要

トランプ新政権が検討・発表している主な関税政策には、次のようなものがあります!
- 中国からの輸入品に対する追加関税の引き上げ(一部商品で30%以上)
- 自動車や自動車部品への関税引き上げ(現在の2.5%から10〜25%へ)
- 鉄鋼・アルミニウムへの高関税の継続と対象国の拡大
- デジタル製品やハイテク機器への新たな関税の検討
これらの政策は、「米国の製造業を復活させる」「貿易赤字を減らす」「国内雇用を守る」といった目的で進められています。
特に日本との関係で注目すべきは自動車関連の関税です。
日本はトヨタ、ホンダ、日産など世界的な自動車メーカーを持ち、米国へ多くの車や部品を輸出しています。
もし自動車関税が大幅に引き上げられれば、日本の自動車産業に大きな影響が出ることは間違いありません。
日本の対米輸出の中で、自動車・自動車部品は約20%を占めており、機械が17%、電子機器が15%と続いています。
このように、関税の影響を受けやすい製造業品目が日本の対米輸出の大部分を構成しているのです。
日本経済への直接的影響
日本の対米輸出の約20%を占める自動車産業。
関税が引き上げられると、次のような影響が考えられます。
自動車メーカーへの影響
関税引き上げにより、日本から米国へ輸出する車の価格が上昇します。
例えば、300万円の車が10%の追加関税で30万円値上がりすることになります。これにより米国での販売台数が減少するリスクがあります。
現在の関税率2.5%では、300万円の乗用車は7.5万円の関税がかかり、販売価格は307.5万円です。これが新関税10%になると30万円の関税となり、販売価格は330万円に。
さらに25%になった場合は75万円の関税で、販売価格は375万円にまで跳ね上がります。
部品メーカーへの波及
完成車だけでなく、部品にも関税がかかれば、日本の中小企業を含む多くの部品メーカーにも影響が及びます。
米国内生産への影響
トヨタやホンダなど、すでに米国内に工場を持つ日本企業は、米国内での生産を増やすよう圧力を受けるでしょう。
これにより、日本国内の生産が縮小する可能性もあります。現在、日系自動車メーカーの米国市場向け車両の生産は、トヨタが約60%、ホンダが約70%、日産が約55%を米国内で行っています。
また、食品や電子機器など、自動車以外の産業にも関税の影響は広がる可能性があります。特に日本が強みを持つ半導体製造装置や精密機器なども、将来的な関税対象となれば大きな打撃となるでしょう。
間接的な経済影響

関税の影響は直接的なものだけではありません。世界経済全体に与える間接的な影響も見逃せません。
サプライチェーンの混乱
現代の製造業では、一つの製品が複数の国を行き来して作られることが普通です。関税が上がると、このグローバルなサプライチェーンが混乱し、生産コストの上昇や納期の遅れなどの問題が生じます。
例えば、日本で作られた部品がアメリカで組み立てられ、その製品が再び日本に輸入されるというケースもあります。関税が上がると、こうした複雑なサプライチェーンの流れ全体に影響が出るのです。
為替への影響
貿易摩擦が激化すると、一般的に「安全資産」とされる円に資金が流入し、円高になる可能性があります。円高になると日本の輸出産業にとってはさらなる逆風となります。
過去の貿易摩擦でも円ドルレートは大きく変動しました。1985年のプラザ合意後は1ドル=240円から150円へ、1995年の日米自動車摩擦時は1ドル=100円から80円へ、2018年の前トランプ政権時も1ドル=110円から105円へと円高が進みました。
世界経済の減速リスク
大国間の貿易摩擦は世界経済全体の成長を鈍らせる可能性があります。日本のような輸出依存度の高い国にとって、これは大きな懸念材料です。
世界の貿易量と経済成長率には強い相関関係があり、貿易摩擦によって貿易量が減少すると、世界経済の成長率も低下する傾向があります。
私たちの生活への影響
では、これらの動きは私たち一般の生活にどう影響するのでしょうか?
物価への影響
アメリカ製品や、アメリカを経由して日本に入ってくる商品の価格が上昇する可能性があります。例えば、アップル製品やアメリカブランドの衣料品、食品などです。
具体的には、電子機器は5~10%程度の価格上昇が予想され、3万円のスマートフォンが3.3万円になる可能性があります。衣料品は10~15%上昇するかもしれず、8千円のジーンズが9千円に。食品・飲料も8~12%上昇し、500円のコーヒーが550円になるかもしれません。
雇用への影響
輸出産業で働く方々の雇用状況が不安定になる可能性があります。特に自動車関連企業や、その下請け企業で働く方々は注意が必要でしょう。
日本の自動車関連産業では約550万人(関連産業含む)が働いており、これらの雇用が影響を受ける可能性があります。
投資環境の変化
株式市場や為替市場の変動が大きくなり、個人投資家の方々も影響を受ける可能性があります。米国株や為替連動型の金融商品を持っている方は特に注意が必要です。
旅行への影響
円高になれば海外旅行がお得になる一方、観光業など国内のサービス業には逆風となる可能性があります。
例えば1ドル=140円から120円へと約14%円高になった場合、アメリカ旅行でのホテル代(1泊200ドル)は28,000円から24,000円に下がります。輸入品も100ドルの商品が14,000円から12,000円に安くなります。一方で、輸出企業は約1割の減益リスクがあり、インバウンド観光客も日本滞在コストの相対的上昇により減少する可能性があります。
日本政府・企業の対応策

このような状況に対して、日本政府や企業はどのように対応しているのでしょうか?
政府の対応
日本政府は米国との交渉を継続し、自動車や鉄鋼などの重要品目について関税引き上げの除外や緩和を求めています。同時に、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)など他の経済圏との連携も強化しています。
日本はこれまでにTPP、日EU経済連携協定(EPA)、地域的な包括的経済連携(RCEP)など多くの貿易協定を結んでおり、米国市場への依存度を下げる取り組みを進めています。
企業の対応
日本企業は生産拠点の見直しを進めています。米国向け製品は米国内で生産する体制を強化し、同時にアジアや欧州など他の市場への展開も加速させています。
企業の対応戦略は様々です。トヨタやホンダのように米国内生産を強化する企業、中小製造業のように第三国経由での輸出を検討する企業、パナソニックやソニーのようにアジア市場強化に舵を切る企業、日立や三菱電機のように事業多角化を進める企業など、各社が自社の強みを活かした戦略を展開しています。
新たな産業育成
日本政府は半導体や再生可能エネルギーなど、将来性のある産業への支援を強化し、米国市場への依存度を下げる取り組みも行っています。
半導体産業には約5兆円、再生可能エネルギー分野には約3兆円の予算が投じられるなど、次世代産業の育成に力を入れています。
まとめ

トランプ政権の関税政策は、短期的には日本経済に逆風となる可能性が高いですが、長期的には日本企業の体質強化や新たな市場開拓のきっかけになるかもしれません。
過去を振り返ると、日本はオイルショック、バブル崩壊、リーマンショックなど多くの経済危機を乗り越えてきました。GDP成長率は一時的に落ち込んでも、やがて回復してきた歴史があります。
私たち一般の生活者としては、次のような点に注意しておくとよいでしょう:
- 輸入品の価格上昇に備えた家計の見直し
- 自分の働く業界が関税の影響を受けるか確認
- 投資ポートフォリオの地域分散を検討
- 円高メリットを活かした海外商品の購入や旅行計画
- 長期的な視点での家計管理
そして最後に覚えておきたいのは、世界経済はいつも変化し続けているということ。かつての日米貿易摩擦の時代も、リーマンショックの時も、日本経済は危機を乗り越えてきました。今回の関税問題も、長い目で見れば必ず適応策が見つかるはずです。冷静に情報を集め、賢く対応していきましょう。
経済ニュースを読む際は、情報源を複数確認し、短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点で判断することが大切です。
(※この記事は2025年4月時点の情報に基づいて作成されています。政策は変更される可能性があるため、最新情報にご注意ください。)