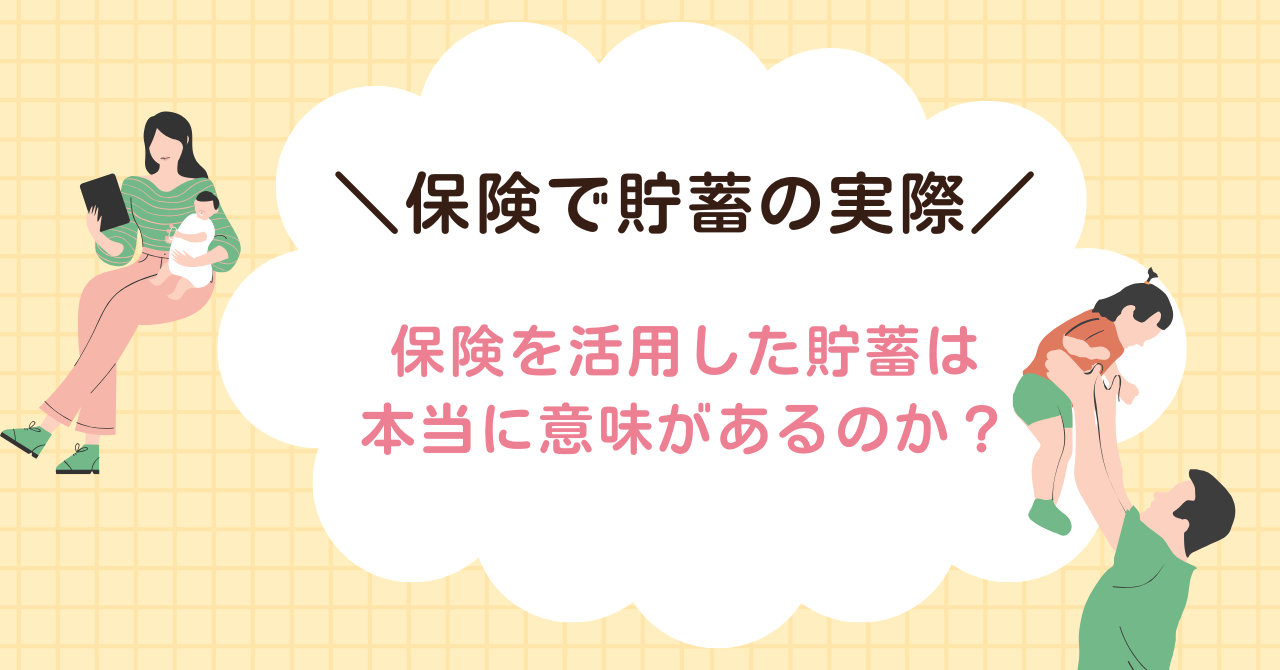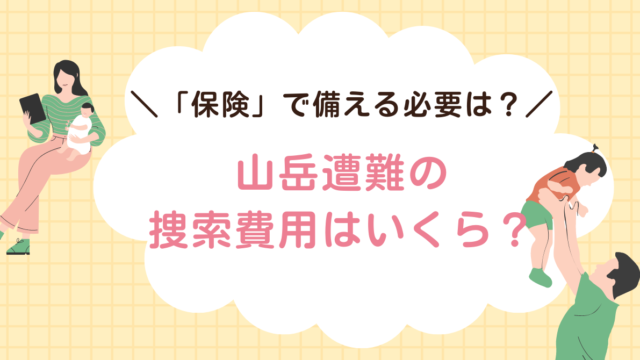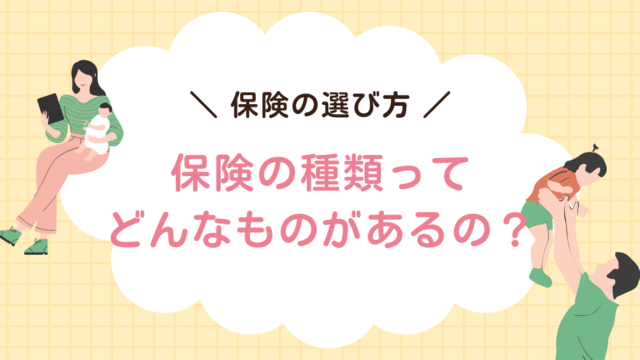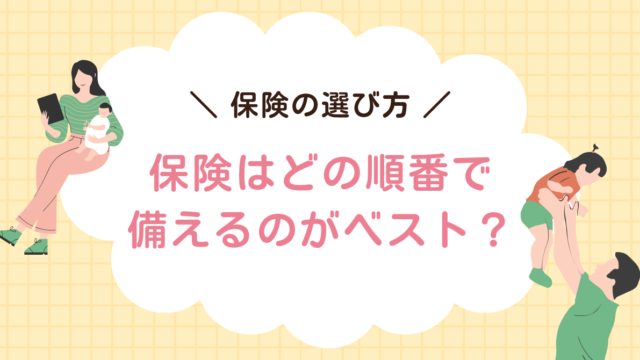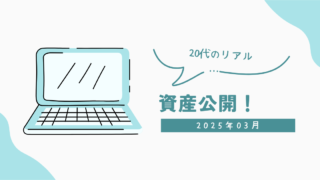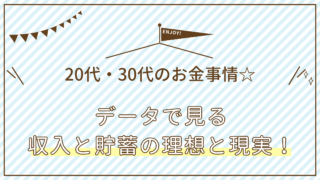みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
保険は本来、リスクに備えるためのものですが、日本では貯蓄性のある保険商品が多く販売されています。
日本人だけではないのかもしれませんが、やはり損はしなくないですもんね、そういった商品には目を惹かれます♪
…しかしこれらは本当に効率的な資産形成手段なのでしょうか?
今回は、多くの方が興味を持つ「保険を活用した貯蓄」についてわかりやすくまとめてみました!
日本人の保険加入状況

まずは、日本人の保険に対する意識を見てみましょう。
生命保険文化センターの調査によると、日本の世帯加入率は約89%と非常に高く、一人あたりの保険料支出も世界的に見て高水準ということがわかります!
| 国名 | 一人あたり生命保険料(米ドル) |
|---|---|
| 日本 | 約3,000ドル |
| アメリカ | 約1,800ドル |
| イギリス | 約2,500ドル |
| ドイツ | 約1,400ドル |
| フランス | 約2,200ドル |
(出典:生命保険協会データ、2023年)
日本人が保険を重視する理由の一つに「貯蓄性」があります。
では、保険を貯蓄手段として活用する意味はあるのでしょうか?
保険を活用した貯蓄の種類
貯蓄性のある主な保険商品には以下のようなものがあります!
- 終身保険:一生涯の保障に加え、解約返戻金という形で貯蓄性を持たせています
- 養老保険:満期時に満期保険金が支払われる貯蓄性の高い保険です
- 個人年金保険:老後の資金を年金として受け取れる保険商品です
- 学資保険:子どもの教育資金を準備するための保険です
これらの商品の市場規模を見ると、2023年時点で個人保険の保有契約高は約900兆円に達しています。その中でも貯蓄性の高い個人年金保険の年間新契約件数は約120万件となっています。
税制上のメリット:控除について

保険を貯蓄手段として活用する大きな魅力はなんといっても税制上の優遇措置があることでしょう。
とりあえず損をしないから。というだけではなくしっかりと制度を理解するとより大切さであったり、自分に合った使い方を考えることができますよ(*’▽’)
生命保険料控除の仕組み
生命保険料を支払うと、所得税と住民税の計算において「生命保険料控除」を受けることができます。平成24年1月1日以降に契約した生命保険の場合は下記のような計算式があります!
所得税の控除額
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,000円超〜40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円超〜80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税の控除額
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 12,000円超〜32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
| 32,000円超〜56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
保険料控除には、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類があり、それぞれで控除を受けられます。そのため、合計で所得税最大12万円、住民税最大7万円の控除が可能です!
具体的な節税効果
年収600万円の会社員(所得税率20%)が、3種類の保険に各8万円、合計24万円を支払った場合を考えてみましょう。
- 所得税控除額:40,000円×3種類=120,000円
- 所得税軽減額:120,000円×20%=24,000円
- 住民税控除額:28,000円×3種類=84,000円
- 住民税軽減額:84,000円×10%=8,400円
- 合計節税効果:32,400円
これは、実質的に保険料の約13.5%が戻ってくる計算になります。
これが、保険上控除の効果といえるでしょう♪
税金の関係
一方で、保険を活用した貯蓄で注意すべき点が利益の扱いです。
日本では、収益が発生したときには基本的に税金がかかります。
その税制度についても知っておくことは大切です!
満期保険金の課税
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
| 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| A | A | 所得税 |
| A | B | 贈与税 |
なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。。。
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。
個人年金の課税
個人年金保険から年金を受け取る場合は、「雑所得」として扱われ、所得税・住民税の課税対象となります。ただし、「公的年金等控除」が適用されるため、一定額までは非課税となります。
公的年金等控除額(65歳以上の場合)
| 年金収入 | 控除額 |
|---|---|
| 330万円以下 | 110万円 |
| 330万円超〜410万円以下 | 年金収入×25%+27.5万円 |
| 410万円超〜770万円以下 | 年金収入×15%+68.5万円 |
| 770万円超 | 年金収入×5%+145.5万円 |
保険を活用した貯蓄と他の金融商品の比較

保険の貯蓄性を評価するには、他の金融商品と比較することが重要です。
20年間の資産形成シミュレーション
以下は、月1万円を20年間運用した場合の最終資産額の比較です。
| 金融商品 | 想定年利 | 20年後の資産額 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.001% | 約240万円 | 安全性最高、流動性高 |
| 定期預金 | 0.02% | 約241万円 | 安全性高、流動性中 |
| 学資保険 | 0.5%程度 | 約250万円 | 税制優遇あり、流動性低 |
| 終身保険 | 1.0%程度 | 約260万円 | 保障あり、税制優遇あり |
| 個人年金保険 | 1.5%程度 | 約270万円 | 税制優遇あり、流動性低 |
| 債券型投資信託 | 2.0%程度 | 約290万円 | リスク中、流動性高 |
| バランス型投資信託 | 4.0%程度 | 約350万円 | リスク中高、流動性高 |
| 株式型投資信託 | 6.0%程度 | 約420万円 | リスク高、流動性高 |
※これらは平均的な数値であり、実際の運用成果は商品や運用期間によって大きく異なります。
保険を活用した貯蓄のメリット・デメリット
メリット
- 税制優遇:生命保険料控除により節税効果がある(年間最大で所得税・住民税合わせて約3万円程度)
- 強制貯蓄:毎月の保険料支払いで自然に貯蓄ができる(解約率データによると、投資信託より継続率が約15%高い)
- リスク保障:貯蓄しながら保障も得られる(死亡時、入院時など)
- 相続税対策:一定の条件下で相続税の軽減効果がある(死亡保険金の非課税枠:法定相続人×500万円)
デメリット
- 低い運用利回り:一般的に投資信託などに比べて利回りが低い(平均して年1〜2%程度)
- 解約時の損失:中途解約すると元本割れする可能性が高い(特に契約初期は解約返戻率が50%以下となることも)
- 流動性の低さ:急にお金が必要になった場合に換金しにくい
- 手数料の高さ:保険会社や代理店の手数料が組み込まれている(初年度の保険料の30〜50%程度が手数料といわれている)
まとめ

保険を純粋な貯蓄・投資手段として見た場合、正直なところ効率は良くありません。金融庁の調査でも、長期的な資産形成には投資信託やETFなどの金融商品の方が、高いリターンが期待できるとされています。
ただし、以下のような方には保険を活用した貯蓄も意味があるでしょう(*’▽’)
- 自己規律を持って貯蓄するのが難しい方:強制貯蓄の仕組みが役立ちます
- リスク許容度が低く、元本保証を重視する方:変動リスクを嫌う方に適しています
- 保障と貯蓄を同時に得たい方:一つの商品で二つの目的を達成できます
- 税制優遇を最大限活用したい方:特に高所得者は節税効果が大きくなります
最適な保険活用のための3つのポイント
- 必要な保障を優先する:まずは生活保障として必要な保険を考え、その上で貯蓄性を検討する
- 長期的視点で加入する:短期解約を前提とせず、10年以上の長期契約を基本とする
- 総合的な資産形成計画の一部として考える:保険、投資、預貯金をバランスよく組み合わせる
多くの方が興味を持つ「保険を活用した貯蓄」についてまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。
最終的には、ご自身の状況や目的に合わせて、保険、投資信託、預貯金などを適切に組み合わせることが重要です。保険は「貯蓄の全て」ではなく、総合的な資産形成の「一部」として考えるのが良いでしょう。