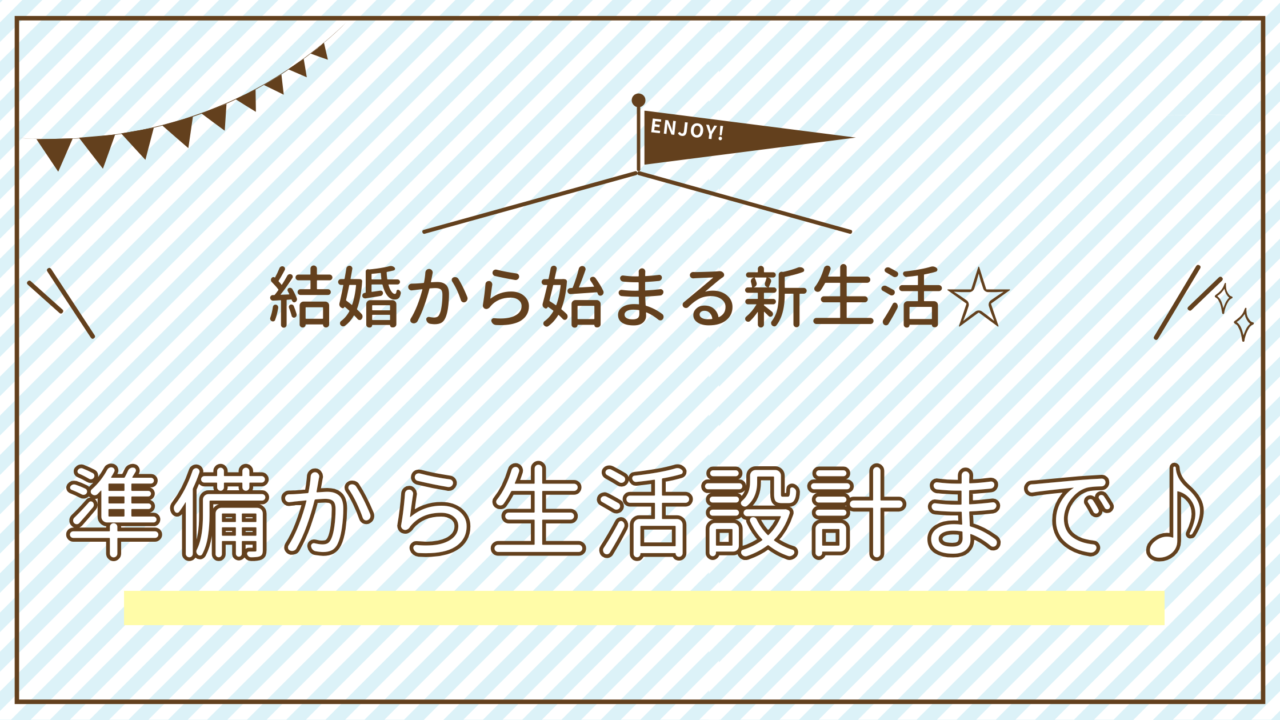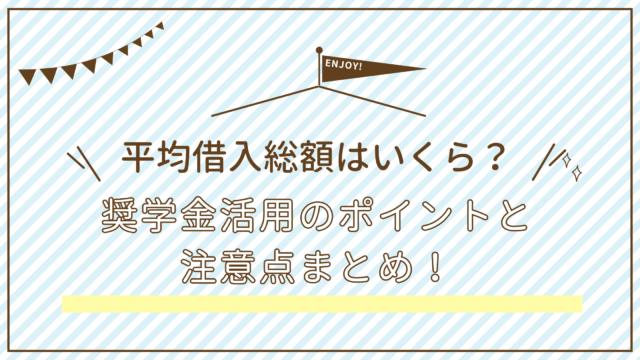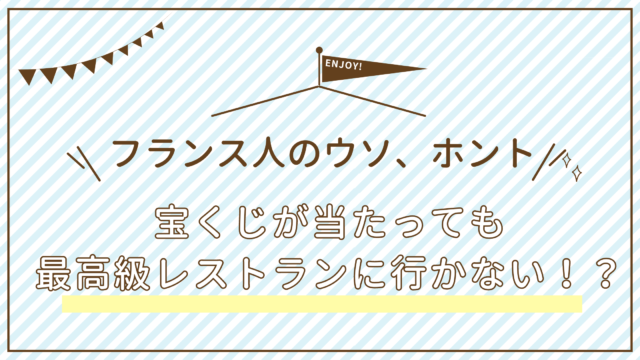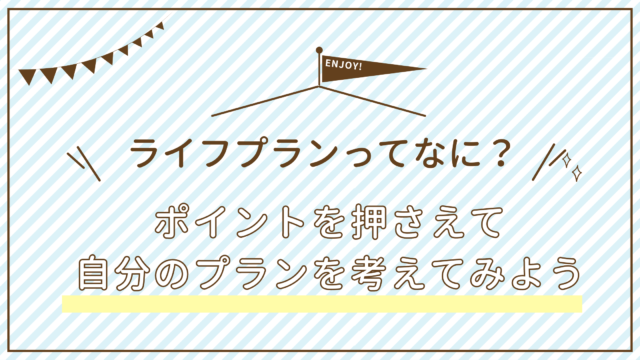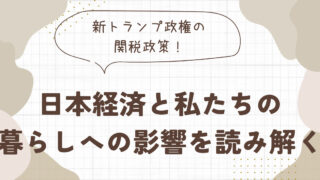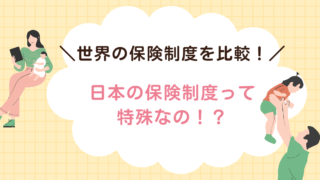みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
結婚は人生の大きな節目であり、同時に財政的にも大きな変化をもたらす出来事ですよね。
気になることはたくさん出てくるかと思います。
今回は、婚約から結婚後の新生活まで、必要な準備と知っておくべき情報を、特に資金計画の視点からわかりやすくまとめてみました♪
婚約から結婚式までの準備

結婚式の費用相場
結婚式の費用は地域や規模によって大きく異なりますが、2024年の全国平均では結婚式全体で約350〜400万円かかると言われています。これはゲスト1人あたり約4万円の計算です。
披露宴会場費は約100〜150万円、衣装・美容費は約80〜100万円、指輪は約30〜50万円が一般的な相場となっています。
資金計画のポイント
結婚式の費用は、カップルにとって最初の大きな共同支出となります。
計画的な資金準備が必要でしょう。おすすめの方法としては、結婚式用の専用口座を作り、毎月一定額を積み立てることです。
例えば、月10万円を1年半続ければ、180万円の資金が準備できます。
また、ボーナスの一部を結婚式資金に充てる計画も立てておくと良いでしょう。
予算配分のコツ
多くのカップルが結婚式後に「もっとここにお金をかければよかった」あるいは「ここはそれほど必要なかった」と後悔する声を聞きます。一般的に優先度が高いと言われるのは、写真・ビデオ撮影といった一生の思い出になるものや、ゲストへのおもてなし(料理、飲み物)です。
一方、招待状は手作りやウェブ招待状の活用、引き出物は実用的でコストパフォーマンスの高いものを選ぶなど、工夫次第で節約できる部分もあります。
新生活のための住まい選び
賃貸と購入の比較
新婚生活を始めるにあたり、住まいを賃貸にするか購入するかは大きな決断です。
賃貸は初期費用が比較的低く(約家賃4〜6ヶ月分)、住み替えが容易で、建物維持費用の心配も少ないというメリットがあります。
一方、購入は資産形成になり、ローン完済後は家賃支出がなくなり、自由にリフォームできるといったメリットがあります。
住居費の適正額と地域別家賃相場
一般的に、家計における住居費の適正比率は収入の25〜30%以内とされています。
例えば、世帯年収600万円の場合、月々の適正住居費は12.5〜15万円程度、住宅ローンの場合は3,000〜3,500万円(金利1%、35年返済の場合)が目安となります。
地域別の家賃相場は以下の表の通りです。
| 地域 | 2LDKの家賃相場(2024年) |
|---|---|
| 東京23区 | 15〜25万円 |
| 大阪市内 | 8〜15万円 |
| 名古屋市内 | 7〜14万円 |
| 地方中核都市 | 5〜10万円 |
住宅ローン選びのポイント
住宅購入を検討する場合、住宅ローン選びは非常に重要です。
固定金利と変動金利のどちらが長期的に有利か、団体信用生命保険の内容、繰り上げ返済の条件、手数料体系などをしっかり比較検討することが大切です。
近年は、金利タイプの選択肢も増え、固定期間選択型や全期間固定型など、ライフプランに合わせた選択ができるようになっています。
新婚生活の家計管理方法

家計管理の方式と特徴
新婚生活での家計管理には、主に3つの方式があります。
完全共有方式は、すべての収入を共有口座に入れて管理する方法で、透明性が高い反面、プライベート支出に制約を感じることもあります。
部分共有方式は、共通費用は共有口座から支出し、個人的な支出は別口座から行う方法で、バランスが取れている反面、管理がやや複雑です。
分担方式は、費目ごとに担当を決める方法で、シンプルですが、収入差がある場合に不公平感が生じることもあります。
夫婦世帯の支出構成比
夫婦世帯の支出構成比の全国平均(2024年データ)は以下の表のようになっています!
| 費目 | 支出構成比 |
|---|---|
| 住居費 | 28% |
| 食費 | 25% |
| 水道光熱費 | 7% |
| 通信費 | 5% |
| 交通費 | 6% |
| 娯楽・交際費 | 11% |
| 被服費 | 5% |
| 保険・医療費 | 8% |
| 貯蓄 | 15% |
これらの比率は平均値であり、実際の家計では地域や生活スタイルによって大きく異なることがあります。
最近では、家計簿アプリやペイロールカード、家計シミュレーターツールなど、デジタルツールを活用して効率的に家計管理を行うカップルも増えています。
結婚に伴う各種手続き
必須手続きリスト
結婚後はさまざまな手続きが必要になります。
まず、婚姻届の提出が基本となりますが、自治体によっては記念品がもらえることもあります。
次に、健康保険の切り替え(扶養に入る場合)、住民票の変更、銀行口座・クレジットカードの名義変更(必要な場合)、マイナンバーカード・運転免許証の更新などが必要です。
税金関連では、源泉徴収票の扶養控除変更、生命保険の受取人変更、ふるさと納税の検討などが重要です。
また、名字が変わる場合は、パスポート、各種会員カード、職場での社内システム、SNSアカウントなど、多岐にわたる変更手続きが必要になります。
| 手続きのタイミング | 必要な手続き |
|---|---|
| 結婚後すぐ | 婚姻届の提出、健康保険の切り替え、住民票の変更 |
| 1ヶ月以内 | 銀行口座・クレジットカードの名義変更、マイナンバーカード・運転免許証の更新 |
| 3ヶ月以内 | 源泉徴収票の扶養控除変更、生命保険の受取人変更 |
| 必要に応じて | パスポート更新、各種会員カード更新、SNSアカウント変更 |
結婚後の保険見直し
結婚後は保険の見直しも重要です。
生命保険の受取人変更、医療保険の見直し、所得補償保険の検討などが基本となります。
また、新たに共済保険、火災保険、自動車保険の家族限定特約などを検討することもおすすめです。
特に、お互いの職業や収入、将来設計によって、必要な保障内容は大きく変わってきますので、専門家に相談することも有効です。
円満な結婚生活のためのコツ

お金に関する対話の重要性
お金に関する対話は、円満な結婚生活を送るための重要な要素です。定期的な家計会議を設けることをおすすめします。
例えば、月1回の支出確認、3ヶ月に1回の中期計画確認、年1回の長期計画と目標達成度確認などを行うことで、お互いの認識のずれを防ぐことができます。
金銭感覚の違いへの対応
日本FP協会の調査によると、約65%のカップルが「お金に関する価値観の違い」を経験しています。
例えば、貯蓄重視派と生活の質重視派、リスク回避型とリスク許容型、長期計画型と短期享受型など、様々な価値観の違いがあります。
これらの違いに対応するためには、小額の「自由に使えるお金」を互いに確保すること、大きな支出は事前に相談するルールを作ること、資産形成の目標を共有することなどが効果的です。
お互いの価値観を尊重しながらも、共通の目標に向かって進むことが大切です。
将来設計の考え方
ライフイベントごとの資金計画
将来設計を考える際には、ライフイベントごとの資金計画が重要です。
主なライフイベントと必要資金(平均値)は以下の表のようになります。
| ライフイベント | 必要資金(平均値) |
|---|---|
| 子育て(0〜22歳) | 約1,000〜1,500万円/人 |
| マイホーム購入 | 約3,500〜4,500万円 |
| 老後資金 | 約2,000〜3,000万円(公的年金以外に必要な額) |
これらの資金を効率的に準備するためには、計画的な資産形成が必要です。
資産形成の基本戦略
資産形成の基本戦略としては、ステップアップ式投資法が効果的です。
まず、緊急資金の確保(生活費の3〜6ヶ月分)を最優先します。次に、住宅資金・教育資金の準備、老後資金の積立を行い、最終的に資産運用(分散投資)に取り組むという流れです。
近年注目されているのは、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用です。NISAでは年間の非課税投資枠が120万円あり、非課税期間は無期限となっています。夫婦で活用すると効果的です。
一方、iDeCoは掛金が全額所得控除となり、運用益が非課税、受取時も税制優遇があるなど、多くのメリットがあります。
まとめ

婚約から結婚後の新生活まで、必要な準備と知っておくべき情報を、特に資金計画の視点からまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
結婚は人生の大きな転機であると同時に、共同の人生設計をスタートさせる機会でもあります。
自分たちにあった形を見つけるために話し合いをしっかり行い、いいスタートを切りましょう(*’▽’)