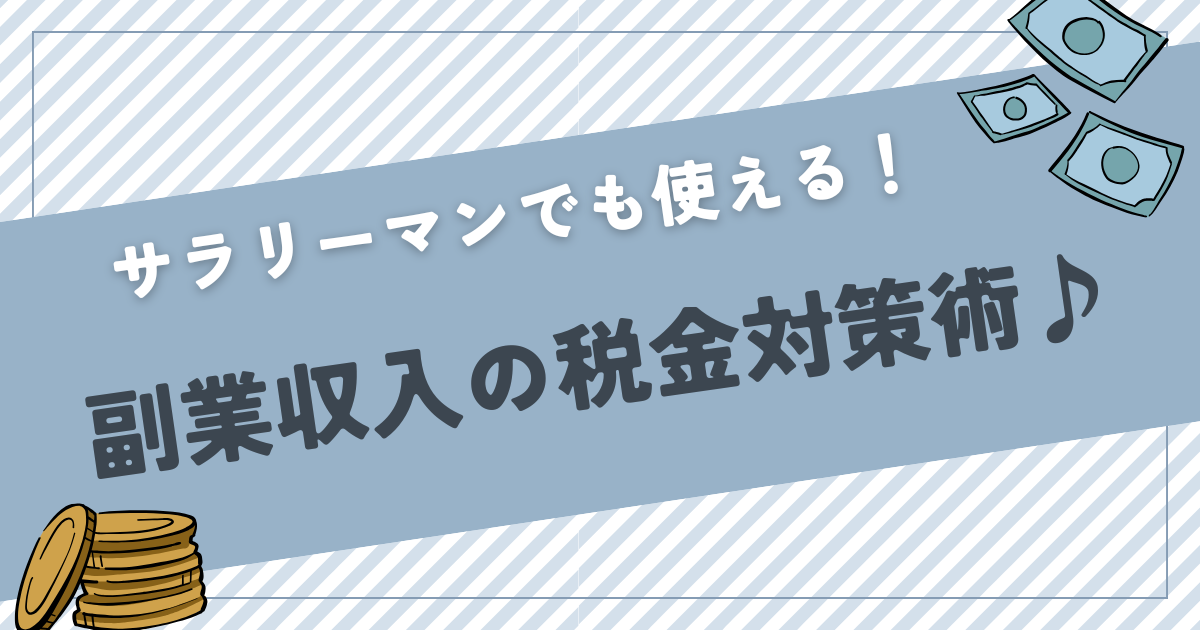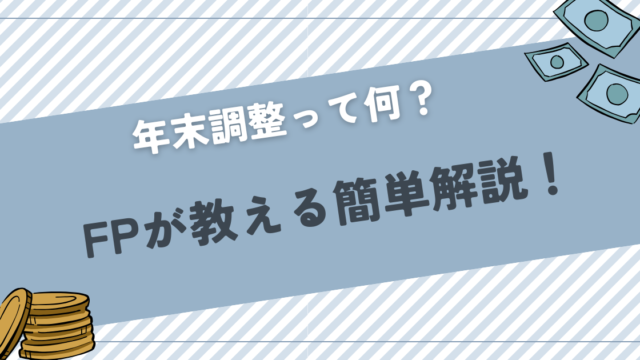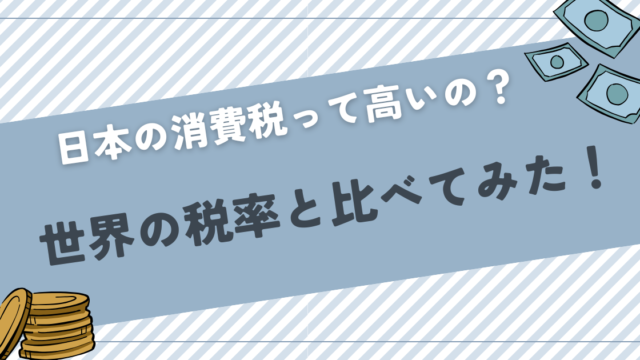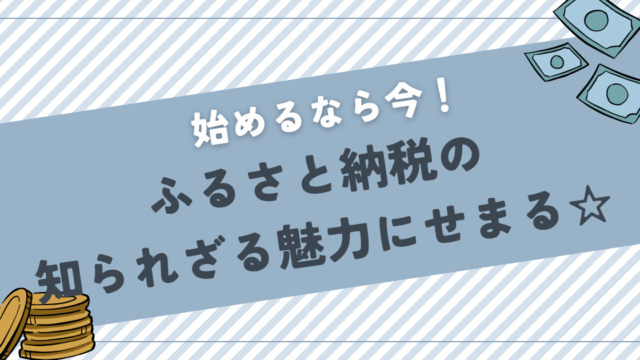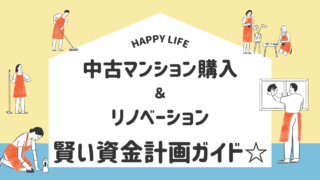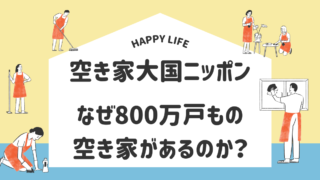みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
近年、副業を始めるサラリーマンが急増しています。経済産業省の調査によると、2024年には働く人の約34%が何らかの副業を持っているとされ、5年前と比較して約1.5倍に増加しました!
しかし、せっかく頑張って得た副業収入も、税金対策を誤ると思わぬ負担になることがあります。。。
実は、副業で得た20万円の収入に対して、適切な税金対策をしないと最大で40%近くが税金として持っていかれることも。。。逆に、正しい知識を持って対策すると、納税額を合法的に30%以上削減できるケースもあるのです(*’▽’)
今回は、FPの視点から副業収入にまつわる税金の基礎知識から実践的な対策までをわかりやすくまとめてみました♪
副業収入の税金基礎知識

副業収入の分類を理解しよう
副業収入は主に以下の3つに分類されます。
- 給与所得:会社員としての副業(例:別の会社での非常勤講師)
- 事業所得:継続的・反復的な事業活動による所得(例:フリーランスの仕事)
- 雑所得:上記に当てはまらない臨時的な所得(例:ポイントサイト、単発の執筆)
この分類によって適用される控除や経費計上の範囲が変わってきます。
多くの副業は「雑所得」として扱われることが多いですが、規模や活動内容によっては「事業所得」になることもあります。
確定申告が必要な基準
副業収入が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。これは所得ではなく「収入」の金額なので注意が必要です。
例えば、50万円の収入があり、経費が35万円だった場合、所得は15万円ですが、収入が20万円を超えているため確定申告が必要です。
<確定申告が必要なケース>
- 副業の年間収入が20万円を超える
- 複数の給与所得があり、第二以降の給与の全てについて源泉徴収されていない
- 給与所得と副業所得の合計が年間所得基礎控除額(48万円)を超える
なお、本業の給与収入が2,000万円を超える場合は、いかなる副業収入があっても確定申告が必要です!
経費として認められるものリスト
副業の税金を抑えるカギは「経費」の活用です。
経費として認められるものを知っておくと、課税対象となる所得を減らせます。
副業タイプ別の経費例(認められるもの)
共通して使える経費:
- 仕事用の通信費(インターネット代、電話代):月額費用の業務使用割合
- 参考書籍・雑誌代:1冊3,000円程度なら全額経費可
- 仕事関連のセミナー費用:1回10,000円程度の勉強会費用
- ホームオフィス費用:家賃や光熱費の一部(使用部屋の床面積比率で按分)
ライター・ブロガーの場合:
- パソコン:10万円のPCなら3年間で減価償却
- カメラ機材:5万円以上なら減価償却、それ以下なら全額経費
- 取材交通費:往復交通費の実費
- クラウドストレージ料金:年間6,000円程度
フリーランスプログラマーの場合:
- 開発ソフト代:年間利用料の全額(例:月額4,000円のサブスク)
- クラウドサーバー費用:月額1,500円の使用料
- 技術書籍:1冊7,000円程度の専門書
- 外付けモニター:2万円の機器なら全額経費可
投資収入の場合:
- 証券会社への手数料:取引額の0.5%程度
- 投資情報サービス料:月額2,000円程度のサービス利用料
- セミナー参加費:1回15,000円程度の投資セミナー
経費の記録は5年間保管が必要です。
スマホアプリでレシートを撮影して管理する方法が便利でしょう。
副業形態別の税金対策

フリーランス・個人事業主の場合
フリーランスとして活動する場合、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選択できます。
青色申告のメリット:
- 最大65万円の特別控除(e-Tax利用+電子帳簿保存で適用)
- 30万円未満の減価償却資産の一括経費化
- 赤字の3年間繰越可能
例えば、年間100万円の副業収入がある場合は
- 白色申告:所得100万円 → 税金約15万円
- 青色申告:所得100万円-特別控除65万円=35万円 → 税金約5万円
青色申告を始めるには、開業後2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
投資による副収入の場合
株式投資やFXなどの投資収入には、一律20.315%の税率が適用される「申告分離課税」が適用されます。
投資の税金対策
- NISA:投資収益が非課税
- iDeCo:掛け金が全額所得控除され、運用益も非課税
- 損益通算:株式の損失と利益を相殺できる(3年間の繰越可能)
例えば、株式投資で年間50万円の利益が出た場合
- 通常:50万円×20.315%=約10.2万円の税金
- NISA活用:税金0円(非課税枠内なら)
小規模副業の場合
クラウドソーシングやポイントサイトなどの小規模副業は「雑所得」として扱われます。
雑所得の控除と対策
- 経費は必要経費のみ(青色申告特別控除は適用されない)
- 所得の合算により、本業と合わせた総所得に応じた累進課税率が適用
例えば、年収500万円のサラリーマンが副業で30万円稼いだ場合
- 経費なし:30万円×約30%(限界税率)=約9万円の追加税金
- 経費10万円:20万円×約30%=約6万円の追加税金
確定申告のテクニック
青色申告と白色申告の選択
青色申告には65万円(または10万円)の特別控除がありますが、帳簿の記帳義務など手続きが複雑です。副業の規模に応じて選びましょう。
目安となる収入基準
- 年間収入50万円未満:白色申告でも十分
- 年間収入50〜100万円:10万円控除の簡易青色申告を検討
- 年間収入100万円以上:65万円控除の青色申告がお得
e-Taxの活用法
インターネットでの確定申告「e-Tax」を利用すると、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、添付書類の提出省略などのメリットがあります。
e-Tax利用に必要なもの
- マイナンバーカード+ICカードリーダーまたはスマホ
- または、ID・パスワード方式の事前登録(税務署で発行)
確定申告期間(2月16日〜3月15日)はe-Taxサイトが混雑するため、2月初旬から入力を始めておくことをおすすめします。
よくある質問と対策

「会社にバレたくない」場合の対応
副業を会社に隠したいケースもあるかもしれませんが、税金面では注意が必要です。
知っておくべきポイント
- 確定申告をすると住民税の「普通徴収」か「特別徴収」かを選べる
- 「普通徴収」を選ぶと自分で納付書払いできる(会社経由にならない)
- ただし、多くの会社は就業規則で副業禁止/届出制にしている
調査によると、大企業の約68%が副業を容認する方針に変わってきていますが、会社のルールは必ず確認しましょう。
扶養内で働きたい場合の収入管理
配偶者の扶養に入っている場合、年間収入が103万円(所得38万円)を超えると所得税の配偶者控除が受けられなくなります。
扶養の境界線
- 103万円:所得税の配偶者控除の境界
- 130万円:社会保険の扶養から外れる境界
- 150万円:配偶者特別控除がゼロになる境界
例えば、副業で年間90万円の収入がある場合
- 経費30万円で所得60万円→配偶者特別控除の対象
- 経費60万円で所得30万円→配偶者控除の対象
経費をしっかり計上することで、扶養の範囲内に収めることも可能です。
まとめ
FPの視点から副業収入にまつわる税金の基礎知識から実践的な対策までをまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
副業による収入は、あなたの可能性と経済的自由を広げるチャンスです。しかし、税金対策を怠れば、せっかくの成果の多くが税金として持っていかれてしまいます。
・収入と経費の記録を習慣化する
・領収書・請求書は必ず保管する(電子保存も可)
・副業の年間収入が20万円を超えるなら確定申告の準備をする
・副業規模に合わせて青色/白色申告を選択する
・確定申告は早め(2月中)に準備・提出する
・所得を低く抑えたい場合は、経費となる支出を年内に済ませる
・副業の規模が大きくなったら、法人化も検討する
基礎知識と対策を実践すれば、平均して副業収入に対する税負担を20〜30%軽減できる可能性があります。年間100万円の副業なら、20〜30万円が手元に残る計算です。
正しい知識で適切に節税し、副業を長く続けられる環境を整えましょう。副業は単なる「おこづかい稼ぎ」ではなく、あなたのキャリアや人生を豊かにする貴重な経験になるはずです!