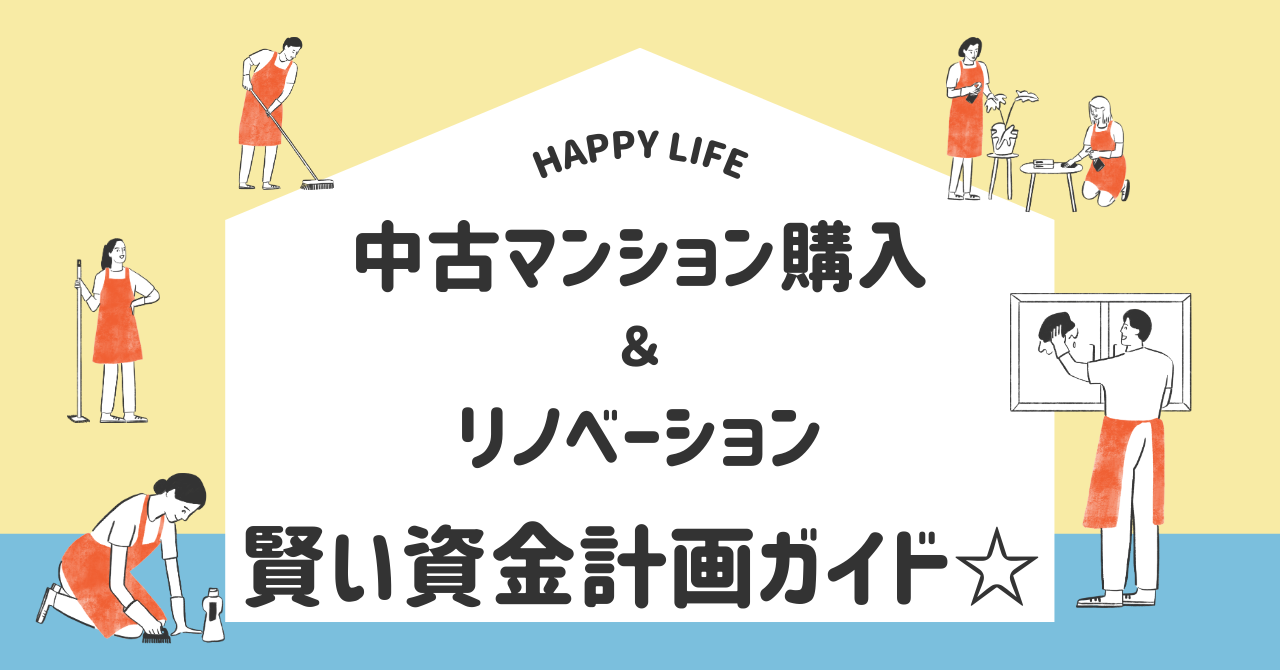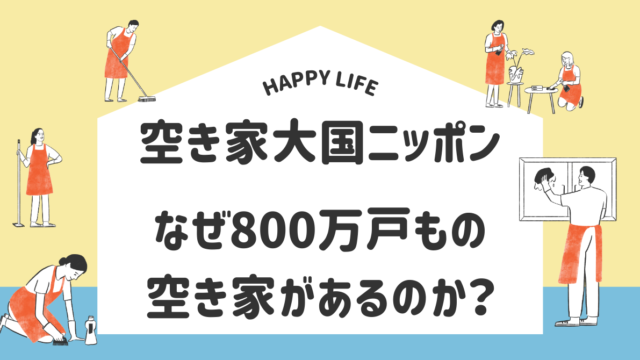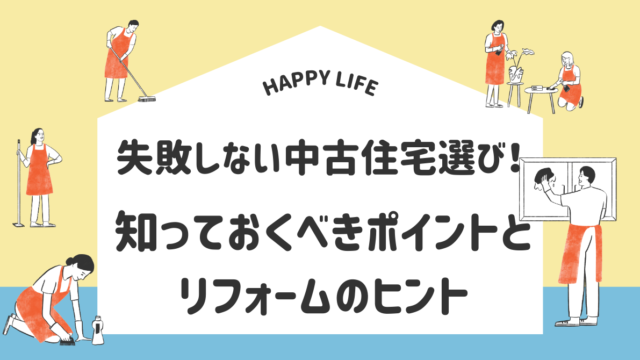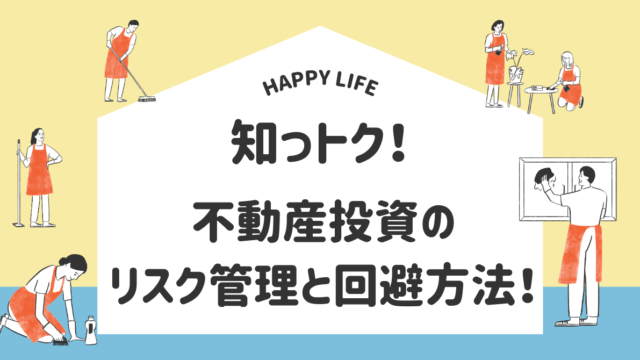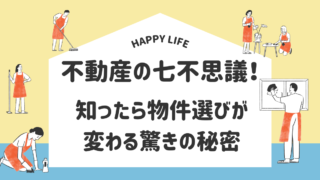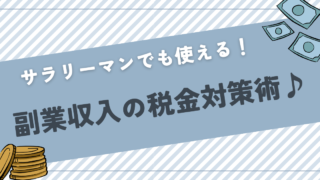みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
中古マンションの購入は、新築と比べて多くのメリットがあります。まず価格面では、同じエリアの新築物件と比較して20~30%程度安く購入できることが魅力的です!特に都心部では、予算内で希望のエリアに住める可能性が高まります。
こうした中古マンションの魅力を最大限に引き出すのがリノベーションです。間取りや内装を自分好みにアレンジできるため、ライフスタイルに合わせた理想の住まいを実現できます。
しかし、中古マンション購入とリノベーションを成功させるためには、綿密な資金計画が不可欠です。
今回は、特にリノベーション一体型ローンの活用法や築年数別の注意点にフォーカスし、失敗しない中古マンション購入のための資金計画についてわかりやすくまとめてみました♪
中古マンション購入とリノベーションの資金計画

中古マンション購入とリノベーションを成功させるためには、まず全体の予算感を把握することが重要です!
物件価格の相場は地域や築年数によって大きく異なりますが、例えば首都圏の中古マンションの平均価格は2024年時点で約4,500万円程度となっています。
一方で、リノベーション費用は規模によって変わりますが、水回りを含む全面リノベーションで100~300万円/坪(約30~90万円/㎡)が一般的な相場です。つまり、70㎡の物件の場合、リノベーション費用だけで約2,100~6,300万円の幅があります。
資金計画を立てる際には、物件価格とリノベーション費用に加えて、諸費用も考慮する必要があります。
具体的には、物件購入時には不動産仲介手数料(物件価格の3~3.3%)、登記費用(約10~15万円)、印紙税(1~3万円程度)、ローン事務手数料(約3~10万円)などがかかります。
さらにリノベーション時には、設計料(工事費の約10~15%)、工事監理料、インテリア費用などを見込んでおく必要があります。
頭金については、一般的には物件価格の2割程度(約900万円)を用意するのが理想的です。これにより、月々の返済負担を軽減できるだけでなく、金融機関からの審査も通りやすくなります。ただし、リノベーション費用も合わせると総額が大きくなるため、頭金とローンのバランスを慎重に検討すべきでしょう。
返済計画については、「年収の25%以内」が無理のない返済額の目安とされています。
例えば世帯年収600万円の場合、月々の返済額は12.5万円以内に抑えることが望ましいということ。ただし、将来の収入変動やライフイベントも考慮し、余裕を持った計画を立てることが重要ですね(*’▽’)
リノベーション一体型ローンの活用法
リノベーション一体型ローンとは、物件購入費用とリノベーション費用を一つのローンで借りられる住宅ローン商品です。通常の住宅ローンでは物件購入費用しか借りられませんが、この商品ならばリノベーション費用も含めた総額を最長35年という長期で借りることができます。
そのため、リノベーション資金を別途用意する必要がなく、月々の返済負担を抑えられるメリットがあります!
リノベーション一体型ローンには主に2種類あります。
まず「フラット35(リノベ)」は、住宅金融支援機構が提供する長期固定金利型ローンです。金利は2024年10月時点で1.55%~2.05%程度ですが、省エネ性能を高めるリノベーションを行う場合には、「フラット35S」として当初5年または10年間、年0.25%の金利引き下げが適用されます。
もう一つは、各民間金融機関が独自に提供するリノベーション一体型ローンで、三菱UFJ銀行の「リノベーションローン」やみずほ銀行の「リノベ de みずほ」などがあります。
従来の住宅ローンとの大きな違いは審査方法にあります。
通常の住宅ローンでは物件価値のみが評価されますが、リノベーション一体型ローンではリノベーション後の物件価値が評価される点が特徴です。そのため、リノベーション計画の内容が審査に大きく影響します。また、リノベーション工事を行う施工会社の実績や信頼性も審査対象となるため、施工会社選びも慎重に行う必要があるでしょう~
具体的な借入例として、築20年・70㎡の中古マンションを3,000万円で購入し、1,500万円のリノベーションを行うケースを考えてみましょう。通常の住宅ローンでは3,000万円しか借りられないため、1,500万円を別途用意するか、高金利のリフォームローンを組む必要があります。
一方、リノベーション一体型ローンなら4,500万円を一括で借り入れでき、例えば金利1.8%、返済期間35年の場合、月々の返済額は約14.5万円となります。
築年数別の注意点と金利交渉術

築年数は住宅ローンの審査や条件に大きく影響します。築年数別の注意点と対策を見ていきましょう。
築10年未満の物件では比較的審査は通りやすく、標準的な金利で借りることができます。
この場合、金融機関の優遇条件を最大限活用することがポイントです。例えば、給与振込口座の開設や公共料金の自動引き落とし設定などで年0.1~0.2%の金利優遇が受けられることがあります。
また、ネット専用住宅ローンを選ぶことで、店舗運営コストの削減分が金利に反映され、年0.2~0.3%程度の金利差が生じる場合もあります。
築10~20年の物件では、将来の大規模修繕を見据えた借入計画が重要です。
マンションの場合、築12~15年目と築25~30年目に大規模修繕が実施されることが多いため、住宅ローンの返済と修繕積立金の増額が重なる可能性があります。そのため、住宅ローンの返済期間や借入額を調整し、将来の負担増に備えることが大切です。
また、物件購入前に建物診断を実施し、構造的な問題がないことを確認することで、金融機関に対して物件の安全性をアピールできます。
築20年以上の物件になると、金融機関の審査が厳格化し、金利の上乗せや融資期間の短縮が行われる傾向があります。
例えば、築30年を超える物件では年0.3~0.5%の金利上乗せや、最長返済期間が20~25年に制限されるケースがあります。
こうした条件に対しては、以下の交渉術が有効です!
- 物件の耐震性や管理状態の良さを示す資料(耐震診断報告書、長期修繕計画書など)を提出
- 複数の金融機関から見積もりを取得し、条件を比較検討
- リノベーションで物件価値が向上することを具体的なプランで示す
- 収入証明や自己資金の充実など、返済能力の高さをアピール
さらに、マンションの管理状態も審査の重要ポイントとなります。
修繕積立金の滞納率が低く、計画的な大規模修繕が実施されているマンションは評価が高くなります。金融機関に提出する資料としては、管理規約、長期修繕計画書、修繕積立金の収支報告書などが必要となるため、購入検討時点でこれらの資料の取り寄せや内容確認を行っておくことをおすすめします。
リノベーション費用を住宅ローンに含める際の注意点
リノベーション費用を住宅ローンに含める際には、いくつかの重要な注意点があります。
まず、金融機関によってリノベーション費用の上限が異なります。一般的には物件価格の30~50%程度までとするケースが多く、例えば3,000万円の物件なら900~1,500万円程度が融資上限となります。
ただし、「フラット35(リノベ)」では物件価格の100%までリノベーション費用を借りられる場合もあります。
審査基準についても金融機関によって差があります。
メガバンクでは資金使途の自由度が比較的高く、内装工事を中心に幅広く対応してくれる傾向がありますが、地方銀行や信用金庫では耐震性向上や省エネ性能の向上など、物件価値を明確に高める工事に限定されるケースが多いでしょう~
物件価値を高めるリノベーション計画を立てることは、審査通過のためにも重要です。
特に以下の要素を含む計画は評価されやすくなります!
- 耐震補強工事(筋交いの追加、壁の補強など)
- 省エネ設備の導入(断熱材の充填、高性能サッシへの交換など)
- 水回りの刷新(キッチン、浴室、トイレなどの最新設備への更新)
- バリアフリー化(段差解消、手すり設置など)
工事業者の選択もローン審査に大きく影響します。
金融機関では、施工実績が豊富で経営状態が安定している業者を好む傾向があります。中には金融機関が提携している施工会社を利用すると審査が有利になるケースも。例えば、三菱UFJ銀行の「リノベーションローン」では、同行が認定した「適合リフォーム業者」を利用することが条件となっています。
また「つなぎ融資」の必要性も理解しておく必要があります。
多くのリノベーション一体型ローンでは、リノベーション工事完了後に融資が実行されるため、工事期間中の資金をどうするかが課題となります。対応策としては、(1)自己資金で工事代金を立て替える、(2)施工会社の後払いサービスを利用する、(3)金融機関のつなぎ融資を利用する、などが考えられます。
つなぎ融資を利用する場合は、金利(年2~4%程度)や手数料(融資額の1~2%程度)も含めた資金計画を立てましょう(*’▽’)
住宅ローン控除とリノベーション費用の関係

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、所得税から一定額が控除される制度です。中古住宅購入とリノベーションにおいても、条件を満たせば適用を受けることができます。
中古マンションの築年数と住宅ローン控除の関係については、以下のような条件があります。
- 木造住宅:築20年以内(耐火建築物の場合は築25年以内)
- 新耐震基準(1981年6月以降に建築確認を受けた建物)に適合していること
ただし、上記条件を満たさない古い物件でも、以下のいずれかを満たせば住宅ローン控除の対象となります。
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入している
- 指定の耐震基準に適合するための工事を行う
- 建設住宅性能評価書で耐震等級1以上を取得している
リノベーション費用を税制優遇の対象とするためには、「増改築等工事証明書」の取得が必要です。この証明書は、(1)50万円超の工事であること、(2)居住用部分の工事であること、(3)一定の工事内容を含むことなどの条件を満たす場合に発行されます。発行には建築士や指定確認検査機関などの証明が必要となるため、工事前に施工会社と相談しておくことが重要です。
特に省エネリノベーションを行う場合には、追加の優遇措置を受けられる可能性があります。「省エネ改修促進税制」を利用すれば、所得税から最大62.5万円の控除や、固定資産税の減額措置を受けることができます。具体的には、窓の断熱改修やLED照明への交換、高効率給湯器の設置などが対象となります。これらの工事を行う場合は、国土交通省が定める「省エネ改修証明書」の取得が必要です。
さらに2024年度税制改正では、「脱炭素化住宅ローン」に関する優遇措置が拡充されました。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準の省エネ性能を備えた住宅については、住宅ローン控除の控除率が0.7%から1.0%に引き上げられ、控除期間も13年に延長されています。中古マンションのリノベーションでZEH相当の性能を達成するのは容易ではありませんが、今後は省エネ性能が高いリノベーションほど税制優遇の恩恵を受けやすくなる傾向にあるため、リノベーション計画時に検討する価値があるでしょう。
金利タイプ別の選び方と交渉術
住宅ローンの金利タイプには主に「変動金利型」と「固定金利型」があり、それぞれ特徴が異なります。
変動金利型は、金融市場の動向に応じて金利が変動するタイプです。2024年10月時点の実質金利は年0.8~1.3%程度と、固定金利型と比べて低いのが特徴です。ただし、将来金利が上昇した場合には返済額も増加するリスクがあります。変動金利は、(1)当面の返済負担を抑えたい、(2)繰り上げ返済を積極的に行う予定がある、(3)金利上昇リスクを許容できる、といった方に向いています。
固定金利型は契約期間中の金利が変わらないタイプです。期間固定金利(3年、5年、10年など期間限定で金利が固定)と全期間固定金利(返済終了まで金利が固定)があります。2024年10月時点の実質金利は、10年固定で年1.5~1.9%程度、フラット35で年1.55~2.05%程度となっています。固定金利は、(1)将来の返済計画を確実に立てたい、(2)金利上昇リスクを避けたい、(3)安定した収入がある、といった方に適しています。
「フラット35」は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローンです。中古物件での利用には、(1)住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していること、(2)築後経過年数が所定の年数以内であることなどの条件があります。ただし、「フラット35(リノベ)」を利用すれば、築古物件でも耐震性や省エネ性などの性能向上リフォームを行うことで融資の対象となります。
金利引き下げ交渉を効果的に行うためには、以下のポイントが重要です!
- 複数の金融機関から見積もりを取得する:競合他社の金利条件を示すことで交渉力が高まります。
- 給与振込や公共料金の自動引き落としなど、付帯サービスを活用する:多くの金融機関では、こうしたサービスの利用で年0.1~0.2%の金利優遇を行っています。
- 取引実績をアピールする:預金残高や投資信託の保有など、銀行との取引実績が多いほど優遇を受けやすくなります。
- 繰り上げ返済の可能性を示す:将来的に一定額の繰り上げ返済を行う意向を伝えると、金利優遇を受けられることがあります。
団体信用生命保険(団信)については、標準的なプランは無料で付帯されることが多いですが、がん保障や三大疾病保障などの特約を付ける場合には追加で年0.1~0.3%程度の金利上乗せとなります。保障内容と費用のバランスを考慮して選択しましょう。例えば、35歳で3,000万円を借り入れる場合、年0.2%の上乗せは総返済額で約100万円の違いになります。健康状態に不安がある場合は保障を厚くする価値がありますが、それ以外の場合は必要最小限の保障に留め、その分を返済額に充てる方が経済的かもしれません。
事例紹介:成功したリノベーション一体型ローン活用例

30代夫婦の都心中古マンション購入&リノベーション事例
山田さん夫婦(夫35歳・年収600万円、妻33歳・年収400万円)は、世帯年収1,000万円で都内の築25年・70㎡の中古マンションを4,200万円で購入し、1,800万円のリノベーションを実施しました。
資金計画:
- 物件価格:4,200万円
- リノベーション費用:1,800万円
- 諸経費:約300万円
- 総費用:約6,300万円
- 自己資金:1,300万円(頭金+諸経費)
- 借入額:5,000万円
ローン選びのポイント:
- メガバンク3行とネット銀行2行から見積もりを取得し比較
- 最終的に変動金利(年0.9%)と10年固定金利(年1.7%)のミックス型を選択
- 半分ずつ組むことで、金利変動リスクのヘッジと当面の返済負担軽減を両立
- 団体信用生命保険は夫婦連生型を選択し、どちらかに万一のことがあっても残債が0になる安心を確保
月々の返済額は約15.5万円で、世帯年収の18.6%に収まり、無理のない返済計画となりました。また、将来的に子どもが小学校に入学するタイミングで教育費が増えることを見越して、当初5年間は余裕資金で繰り上げ返済を行い、総返済額の圧縮を図る計画です。
40代シングルの郊外中古マンション購入&リノベーション事例
佐藤さん(42歳・年収720万円)は、東京郊外の築32年・55㎡の中古マンションを2,200万円で購入し、1,400万円のリノベーションを実施しました。
資金計画:
- 物件価格:2,200万円
- リノベーション費用:1,400万円
- 諸経費:約200万円
- 総費用:約3,800万円
- 自己資金:800万円(頭金+諸経費)
- 借入額:3,000万円
ローン選びのポイント:
- 築32年という築古物件のため、一般の金融機関では金利上乗せや融資期間の制限があった
- 「フラット35(リノベ)」を活用し、耐震性・省エネ性を向上させるリノベーションプランを提出
- 省エネ性能を高めるリノベーションを行ったため、「フラット35S」の金利引き下げ(当初10年間▲0.25%)を適用
- 返済期間を25年に設定し、60歳までに完済する計画を立てた
月々の返済額は約13.2万円で、年収の22%に収まっています。特に注目すべきは、築32年という築古物件であっても、フラット35(リノベ)を利用することで、通常の住宅ローンよりも有利な条件で借り入れできた点です。また、省エネリノベーションを行ったことで、住宅ローン減税に加えて省エネ改修促進税制も適用され、初年度は約45万円の税負担軽減を実現しました。
まとめ
中古マンション購入とリノベーションを成功させるためのチェックリストをまとめます。時系列に沿って確認していきましょう。
物件検討段階(購入3~6ヶ月前)
- 総予算(物件価格+リノベーション費用+諸経費)の設定
- 自己資金の確認と頭金の準備
- 複数の金融機関で事前審査を受け、借入可能額を把握
- 物件の築年数や構造から、適用可能な住宅ローン商品を調査
- 管理規約でリノベーションの制限がないか確認
物件選定段階(購入1~3ヶ月前)
- 建物診断(インスペクション)の実施
- マンションの管理状況書類(長期修繕計画書、修繕積立金の収支報告書など)の取得
- リノベーション業者の選定と見積り取得
- リノベーション後の物件価値を試算
- リノベーション一体型ローン取扱金融機関のリストアップ
ローン申請段階(購入1~2ヶ月前)
- 複数の金融機関から金利・諸条件の見積もりを取得
- 変動金利・固定金利のシミュレーション比較
- 団体信用生命保険のタイプと保障内容の検討
- リノベーション計画書と見積書の準備
- 必要書類の収集(収入証明書、住民票、物件資料など)
契約・実行段階
- つなぎ融資の必要性と調達方法の検討
- 増改築等工事証明書の発行依頼(住宅ローン控除用)
- 省エネ改修証明書の発行依頼(該当する場合)
- 引き渡し日とリノベーション工事スケジュールの調整
- 住宅ローン本審査の申請と契約
これらのチェックポイントを一つひとつ確認していくことで、スムーズな購入とリノベーションを実現できるでしょう。
住宅ローン選びでは、金利の低さだけでなく、繰り上げ返済の手数料や条件、団体信用生命保険の保障内容なども比較検討しましょう。また、中古マンション購入とリノベーションには複数の専門家の協力が必要です。具体的には、不動産仲介業者、リノベーション会社、住宅ローンアドバイザー、建築士、税理士などがサポートしてくれます。これらの専門家選びも成功の鍵となるため、実績や口コミを確認し、相性の良い専門家と協力して進めることをおすすめします。
中古マンション購入とリノベーションには複雑な要素が多いですが、綿密な計画と適切な資金計画があれば、新築には無い魅力的な住まいを実現できます。