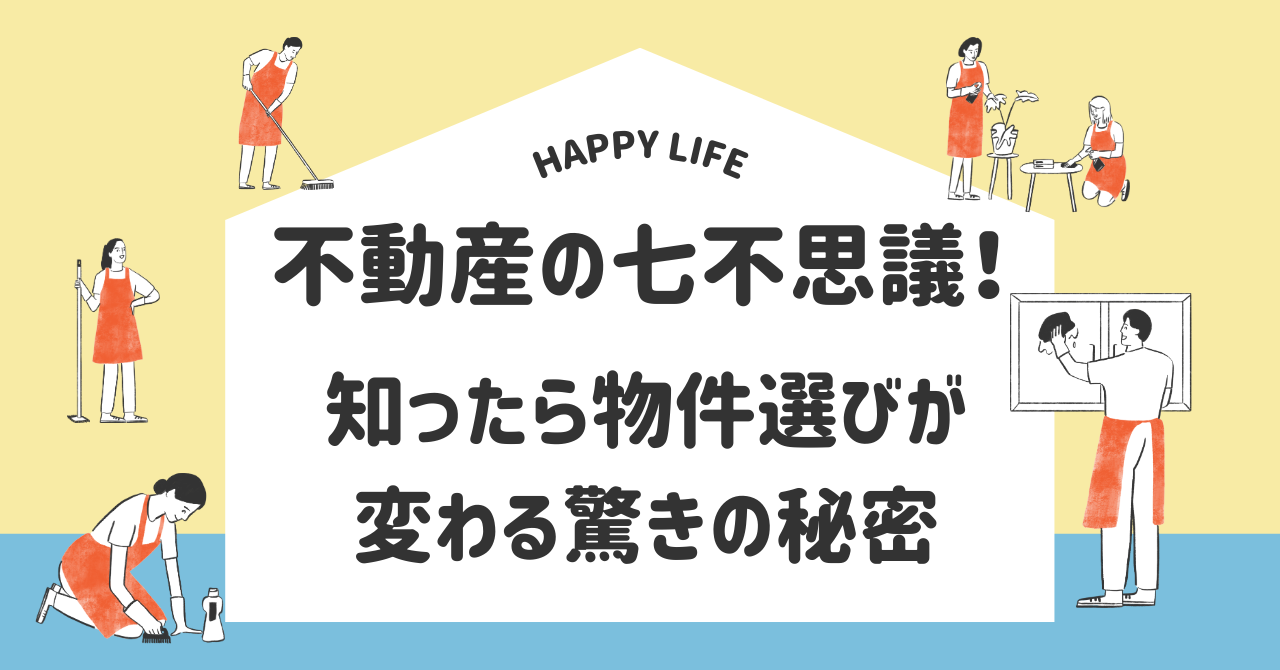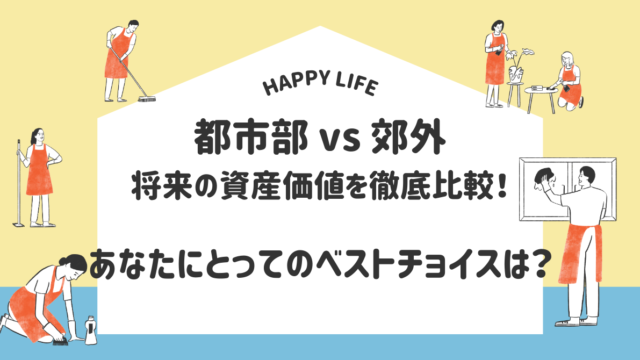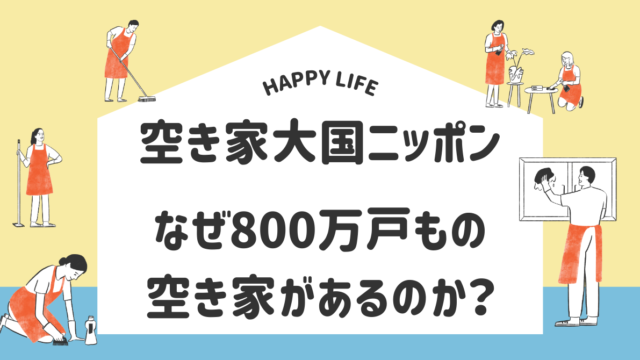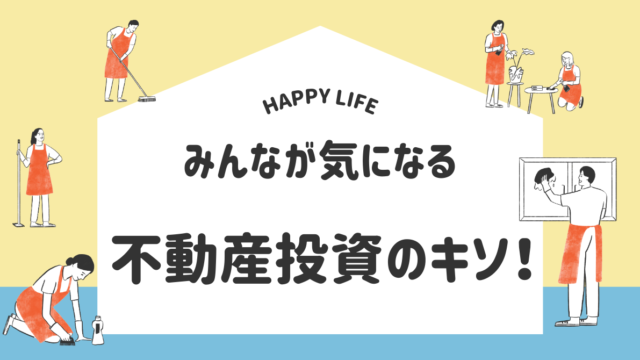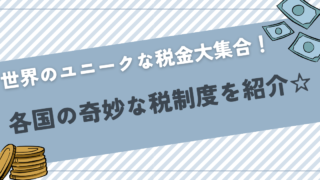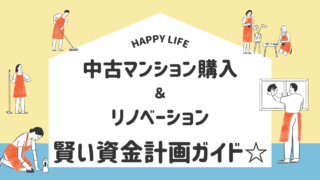みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
「駅から近ければ近いほど良い」「南向きが最高」「角部屋は premium」…不動産選びでよく耳にするこれらの”常識”、本当に正しいのでしょうか?
私はFPとして5年以上、不動産購入相談に乗ってきました。その経験から言えるのは、多くの方が「みんなが言うから」という理由だけで物件選びの基準を決めているという事実です。
人生で最も高額な買い物の一つである不動産。後悔しないためには、「みんなが言うから」ではなく、データに基づいた冷静な判断が欠かせません。
今回は、不動産業界の”常識”とされる7つの迷信について、最新のデータと専門家の視点から検証していきます。これから住まい探しを始める方も、すでに物件をお持ちの方も、きっと「目から鱗」の発見があるはずです。
それでは、不動産の「七不思議」の世界へご案内します!
不思議その1:「角部屋神話」の真実
「角部屋は良い物件」という常識、本当でしょうか?
実は、住宅情報サイトSUUMOの調査によると、角部屋の家賃は同じ物件の中間部屋と比較して平均5~8%高くなっています(出典:SUUMO住みたい部屋ランキング2023)。
しかし、角部屋には知られざるデメリットも。。。
国土交通省の「住宅の断熱性能と冷暖房費に関する調査」(2022年)では、角部屋は中間部屋に比べて冬の暖房費が約10~15%高くなるケースが多いことが報告されています。
角部屋の価値は立地や建物構造によって大きく変わります。
特に東京23区の築10年以内のマンションでは、角部屋プレミアムが賃料に反映されていることが多いですが、郊外の物件では差が小さい傾向にあります。長期的なコスト計算をした上で判断しましょう。
不思議その2:「南向き至上主義」の落とし穴

「南向きが最高!」というのは本当でしょうか?
気象庁の日照データによると、東京都内の年間日照時間は約1,900時間。
しかし都市部の高層ビル群では、理論上の日照時間と実際に部屋に入る日光には大きな差があります(出典:気象庁「地域気象観測システム」2023年データ)。
不動産経済研究所の調査では、都心部のタワーマンションでは、東南・南西向きの部屋が南向きよりも人気が高く、平均3%高い価格で取引される傾向があるとのデータもあります(出典:不動産経済研究所「マンション市場動向調査」2023年版)。
南向きは基本的に良いものの、周辺環境や生活スタイルによっては最適とは限りません。
在宅勤務が増えた現在、西日による室温上昇が気になる方も増えています。物件見学は複数の時間帯で行うことをおすすめします。
不思議その3:「築年数」と「実質的な物件寿命」のミスマッチ
「築古=価値が低い」は単純すぎる考え方です。
日本マンション管理組合連合会の調査によれば、適切な大規模修繕を行っているマンションは、築30年を超えても資産価値の下落率が緩やかになる傾向があります(出典:日本マンション管理組合連合会「マンションの維持管理と資産価値の相関調査」2022年)。
特に注目すべきは「大規模修繕の履歴」です!
国土交通省の調査では、過去30年間に2回以上の大規模修繕を適切に実施しているマンションは、同時期に建てられた修繕不足のマンションと比較して、平均15~20%高い取引価格を維持しているというデータがあります(出典:国土交通省「マンションストック長寿命化等モデル事業報告書」2023年)。
築年数だけでなく、修繕履歴と管理組合の財務状況をチェックすることが重要です。
修繕積立金が適正に設定され、計画的な修繕が行われている物件は、築古でも価値が保たれやすいです。
不思議その4:駅近物件の「隠れたコスト」

駅徒歩1分の物件は本当にお得でしょうか?
東京都環境局の騒音測定データによると、主要駅周辺100m以内のエリアは、昼間の平均騒音レベルが65~75デシベルに達することがあります。
これは一般的な会話(60デシベル)よりも大きな騒音レベルです(出典:東京都環境局「都内の騒音レベル測定結果」2023年)。
また、不動産情報サイトHOME’Sの調査では、「駅近であることよりも静かな環境を優先する」と回答した人が35.7%にのぼり、特に30代以上では増加傾向にあります(出典:HOME’S「住まい選びの価値観調査」2023年)。
駅近物件は確かに便利ですが、駅から徒歩5~7分の物件は騒音レベルが約10デシベル下がる傾向があり、価格も5~10%程度安くなることが多いです。
通勤時間と睡眠の質、どちらを優先するかは生活スタイルによって判断すべきでしょう。
不思議その5:「間取り表記」に隠された真実
「6畳」と表記されていても、実際の使い勝手は大きく異なります。
国土交通省の住宅性能表示制度によれば、同じ6畳の部屋でも、形状によって実際に家具を配置できるスペースは最大で20%も異なることがあります(出典:国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度解説書」2022年版)。
特に注目すべきは「壁芯」と「内法」の違い!!
不動産広告では「壁芯」(壁の中心線)で面積を計算していることが多く、実際に使える面積は広告表記より5~10%小さいことがほとんどです(出典:消費者庁「不動産広告の表示に関する実態調査」2022年)。
間取り図だけでなく、実際の部屋を訪問する際は「動線」をチェックすることが重要です。
リビングから各部屋へのアクセスがスムーズか、家具配置の自由度はどうかを確認しましょう。
不思議その6:「住宅ローン控除」の誤解

多くの方が「住宅ローン控除=得」と思い込んでいますが、実態は異なります。
財務省の統計によれば、住宅ローン控除の平均的な減税額は年間約12~15万円ですが、これは借入額や年収によって大きく変動します(出典:財務省「住宅ローン減税の実績に関する統計調査」2023年度)。
特に注目すべきは2022年以降の制度変更。
年収要件の引き下げや控除期間の短縮により、特に年収800万円以上の世帯では、以前よりも控除額が平均15%減少しています(出典:国税庁「住宅借入金等特別控除に関する統計」2023年)。
住宅ローン控除は「お得だから借り入れを増やす」べきものではありません。シミュレーションでは、多くの場合、頭金を増やして借入額を減らした方が、長期的には総返済額が少なくなります。
住宅ローンは「必要な分だけ借りる」のが基本です。
不思議その7:「不動産価格の謎」
同じエリアでも物件価格に大きな差があるのはなぜでしょうか?
東日本不動産流通機構(レインズ)のデータによると、同じ住所の中古マンションでも、取引価格の差は最大で30%に達することがあります(出典:東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場動向」2023年第4四半期)。
この差の理由として、不動産経済研究所の分析では、「売主の事情」(44.3%)、「物件の個別性」(32.7%)、「取引時期」(23.0%)が挙げられています(出典:不動産経済研究所「不動産価格形成要因分析」2023年)。
物件価格の交渉では、過去の実取引価格データを参考にするのが効果的です。国土交通省の「不動産取引価格情報検索サイト」では、実際の取引価格を無料で調べられます。
また、売主が個人か法人かによっても交渉の余地は変わってきます。
まとめ

不動産業界の”常識”とされる7つの迷信についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
今回のブログ、「七不思議」を踏まえると、物件選びでは次の点に注意すると良いでしょう(*’▽’)
- 角部屋は追加コストに見合うメリットがあるか検討する
- 南向きだけでなく、周辺環境と実際の日当たりを確認する
- 築年数よりも修繕履歴と管理状況をチェックする
- 駅近のメリットと騒音・振動などのデメリットを比較する
- 間取り図の数字だけでなく実際の使い勝手を想像する
- 住宅ローン控除を過信せず、総返済額で判断する
- 相場データを活用して適正価格を見極める
住まい選びは人生で最も大きな買い物の一つです。表面的な情報だけでなく、この「七不思議」の視点を取り入れることで、後悔のない選択ができるでしょう。
※本ブログの内容は2025年3月時点の情報に基づいています。
※データの出典元は各記事内に記載しています。