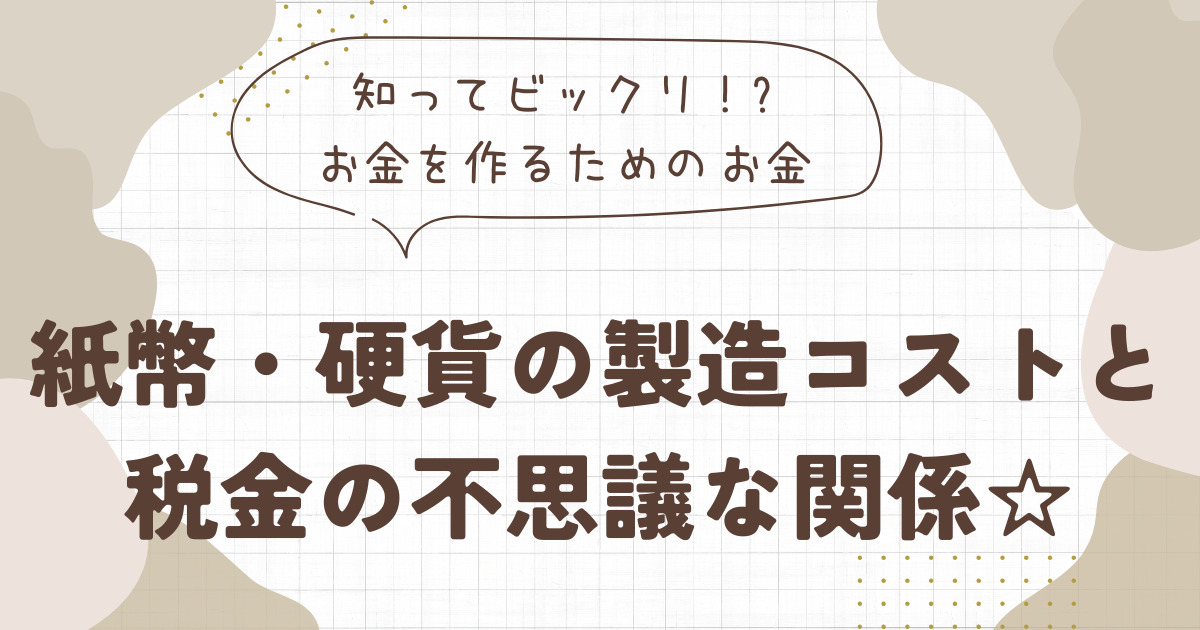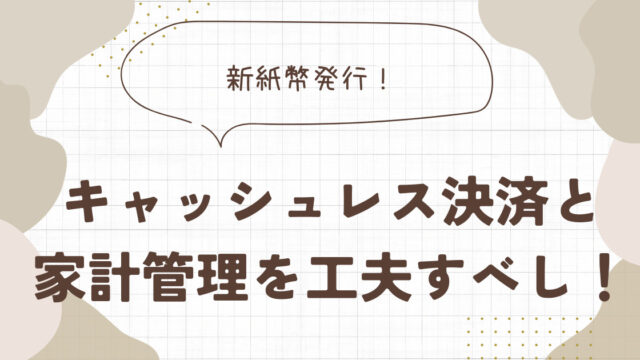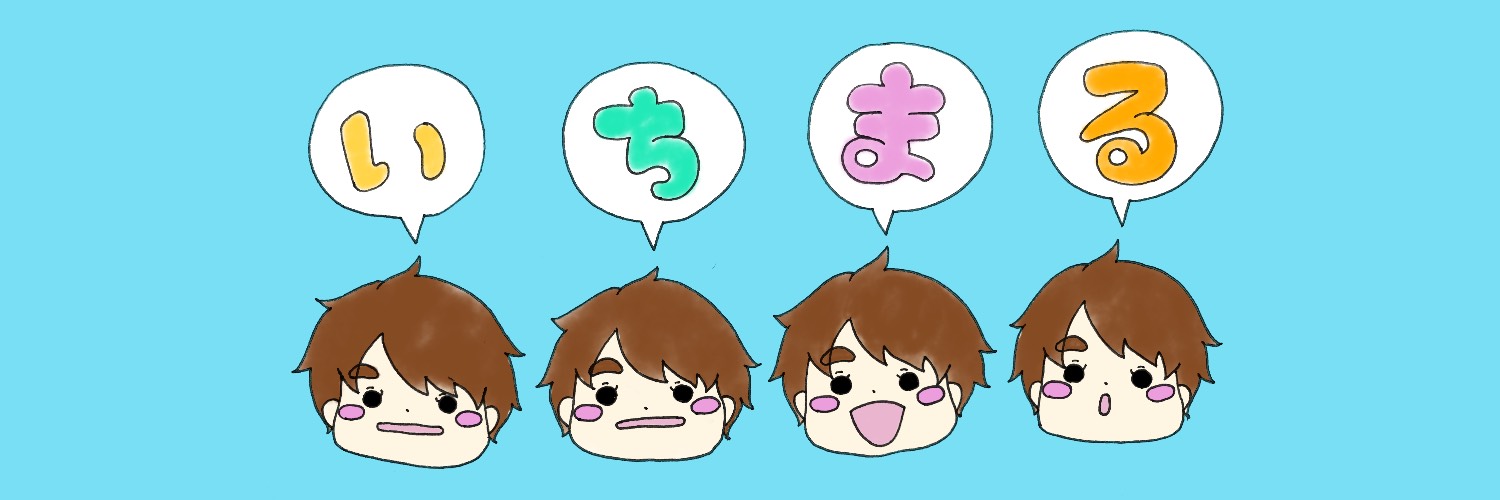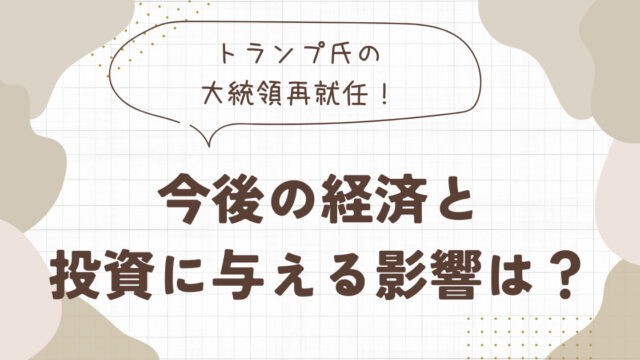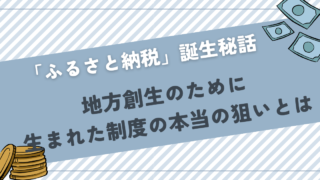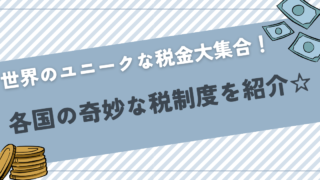みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
普段何気なく使っているお金ですが、「お金を作るのにいくらかかっているか?」と聞かれたら、答えられる方は少ないのではないでしょうか。
実は、私たちが日常的に使用している紙幣や硬貨には、意外にも多くの製造コストがかかっています。例えば、1万円札1枚を作るのに約20円のコストがかかることをご存知でしたか?
今回は、お金を作るためにかかるお金と、その財源となる税金の関係についてわかりやすくまとめてみました♪
紙幣の製造コスト

各紙幣の製造コスト比較
日本の紙幣(1万円、5千円、千円)は、独立行政法人国立印刷局で製造されています。各紙幣の製造コストは以下の通りです。
- 1万円札:約20円/枚
- 5千円札:約17円/枚
- 千円札:約15円/枚
意外と安いと思われるかもしれませんが、年間製造枚数を考えると膨大なコストになります。2023年度の紙幣製造枚数は約30億枚で、総コストは約600億円にも上ります。
特殊インクや偽造防止技術のコスト
紙幣のコストの大部分を占めるのが、偽造防止技術です。
ホログラムや特殊インク、マイクロ文字など、最新の技術を駆使して偽造防止対策が施されています。これらの技術開発や導入には多額の投資が必要ですが、経済の信頼性を保つためには欠かせない費用と言えるでしょう。
紙幣の寿命とコスト効率
紙幣には寿命があるのをご存知ですか?平均的な寿命は以下の通りです。
- 1万円札:約4〜5年
- 5千円札:約2〜3年
- 千円札:約1〜2年
使用頻度が高い千円札は特に傷みやすく、定期的に新札に入れ替える必要があります。この「お金の入れ替え」にもコストがかかっているのです。
硬貨の製造コスト
各硬貨の材料費と製造コスト
硬貨は独立行政法人造幣局で製造されています。
各硬貨の製造コストは以下の通りです。
- 500円:約30円/枚
- 100円:約18円/枚
- 50円:約13円/枚
- 10円:約7円/枚
- 5円:約9円/枚
- 1円:約3円/枚
「額面価値<製造コスト」の1円玉の存在理由
お気づきの方もいるかもしれませんが、1円玉と5円玉は製造コストが額面価値を上回っています。特に1円玉は1円の価値を持つコインを作るのに3円かかるという「赤字製造」の状態です。
それでも製造が続けられる理由は、経済取引の円滑化と国民の信頼確保のためです。
金属価格の変動が硬貨製造に与える影響
硬貨の製造コストは、使用される金属(銅、ニッケル、亜鉛等)の国際市場価格に大きく影響されます。
金属価格が高騰すると、硬貨の製造コストも上昇します。このため、造幣局では材質の研究も常に行われています。
お金の製造は誰が負担しているのか?

日本銀行と造幣局の関係
紙幣は日本銀行の発注に基づいて国立印刷局が製造し、硬貨は財務省の発注に基づいて造幣局が製造しています。
日本銀行は紙幣の製造コストを負担していますが、その資金源は?と考えると複雑になります。
紙幣・硬貨製造コストの財源と税金の関わり
紙幣の製造コストは直接的には日本銀行が負担しますが、日本銀行の利益の大部分は国庫に納付されるため、間接的には国民の税金が使われていると考えることもできます。
一方、硬貨の製造コストは財務省が負担するため、より直接的に税金が使われています。
興味深いのは、通貨発行益(シニョレッジ)という概念です。例えば、20円のコストで1万円札を発行すると、理論上は9,980円の利益が生じます。この「お金を作ることで生まれる利益」は国の重要な収入源となっています。
国民の税金がどう使われているのか
年間の通貨製造コストは約700億円程度と推定されています。
これは国家予算(約100兆円)からすれば1%にも満たない金額ですが、私たちの経済活動を支える重要なインフラ投資と言えるでしょう。
デジタル通貨時代の製造コスト
キャッシュレス化による紙幣・硬貨製造コストの変化
近年のキャッシュレス化により、紙幣・硬貨の流通量は徐々に減少傾向にあります。
これにより製造コストの削減が期待される一方で、現金システムの維持コストは固定費的な側面があるため、単位あたりのコストは上昇する可能性もあります。
デジタル通貨のコスト構造との比較
電子マネーやクレジットカードなどのデジタル決済には、システム開発・維持費、セキュリティ対策費、決済手数料などのコストがかかります。これらのコストは消費者が直接負担することもあれば、加盟店や金融機関が負担することもあります。
現金システムと比較すると、長期的にはデジタル決済の方がコスト効率が良いとされていますが、完全な移行にはまだ時間がかかるでしょう。
今後の展望:CBDCと税金の関係
中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究開発が世界中で進んでいます。日本でも日銀がCBDCの実証実験を行っており、将来的には発行される可能性があります。CBDCが導入されれば、紙幣・硬貨の製造コストは削減される一方で、システム開発・運用コストが発生します。この財源も最終的には国民の税金が使われることになるでしょう。
まとめ

お金を作るためにかかるお金と、その財源となる税金の関係についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
私たちが日常的に使用しているお金には、製造から流通、管理に至るまで様々なコストがかかっています。そして、そのコストの多くは直接的・間接的に税金から賄われています。
現金であれデジタルであれ、通貨システムの維持には相応のコストがかかりますが、それは経済活動を円滑に行うための社会的インフラへの投資と考えることができます。
ファイナンシャルプランナーとしてのアドバイスは、お金の価値は常に変動しているということです。インフレや金利の変動によって、同じ1万円でも実質的な価値は変わります。だからこそ、資産形成においては現金だけでなく、様々な資産に分散して保有することが重要なのです。
※本記事の情報は2025年2月時点のものです。最新の情報については関連機関の公式発表をご確認ください。