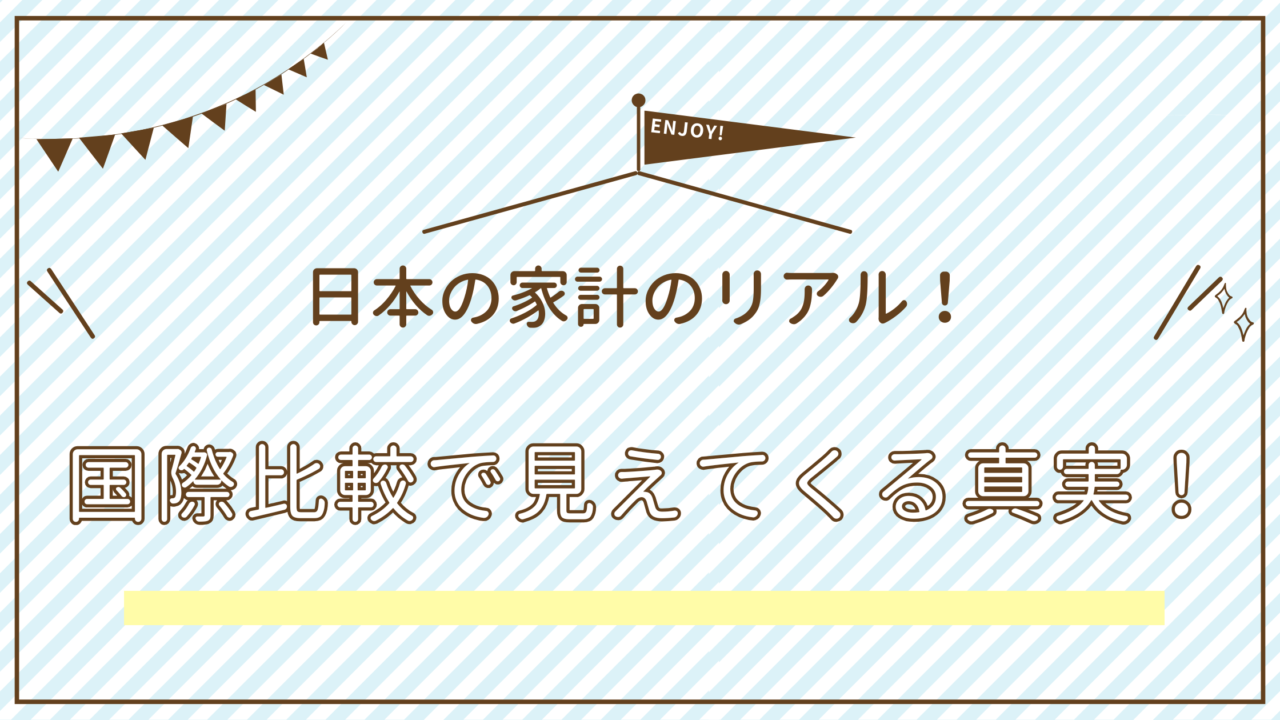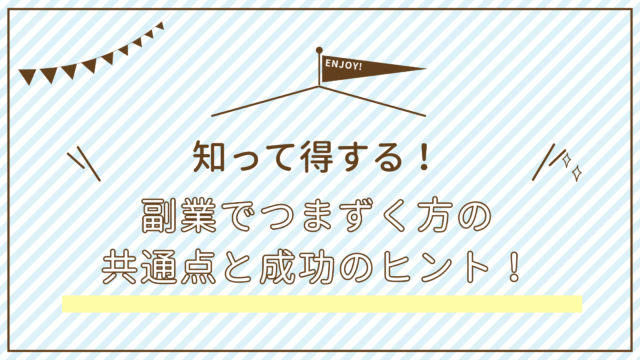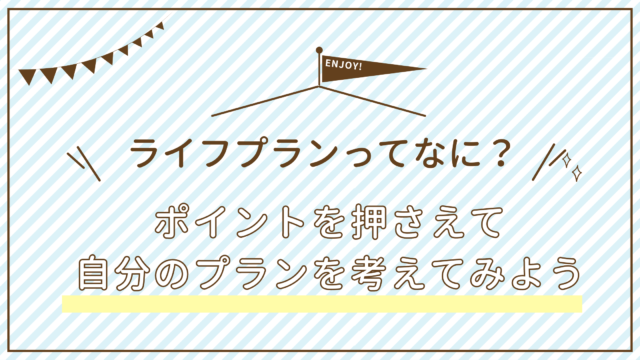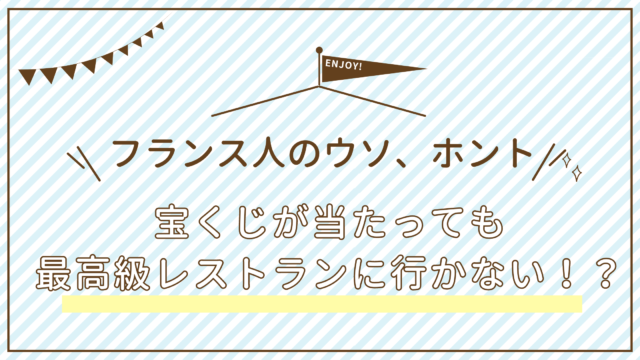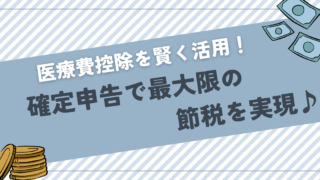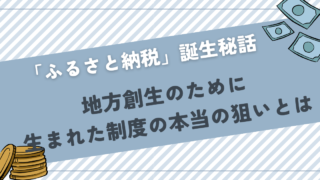みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
「日本人はお金に関してどうなの?」「海外と比べて私たちの家計や投資行動は普通?」このような疑問を持ったことはありませんか?
グローバルな視点で見ると、日本人の金融行動には独特の特徴があり、それが私たちの資産形成にも大きな影響を与えています。
今回は、国際比較のデータから見えてくる日本人の家計事情について、興味深いポイントをわかりやすくまとめてみました!
貯蓄大国日本?家計の貯蓄率を国際比較
日本は「貯蓄大国」と言われているのをご存知でしょうか?
しかし…実は状況が大きく変わってきています!!
どういうことか、早速見ていきましょう。
各国の家計貯蓄率比較(対可処分所得比)
- 日本:3.3%(2023年)
- アメリカ:5.1%(2023年)
- ドイツ:10.9%(2023年)
- フランス:11.5%(2023年)
- イタリア:6.8%(2023年)
- スウェーデン:16.2%(2023年)
- スイス:17.5%(2023年)
【データ出典:OECD「Household savings」(2024)】
日本の貯蓄率の歴史的推移
- 1980年代:15%前後
- 1990年代:10%前後
- 2000年代:5%前後
- 2010年代:3~4%前後
- 2020年代:コロナ禍で一時的に上昇後、再び低下傾向
【データ出典:内閣府「国民経済計算」(2024)】
貯蓄率低下の主な要因分析
1.所得の伸び悩み
平均実質賃金は1997年をピークに長期的に低下傾向
2.高齢化による影響
高齢者は貯蓄を取り崩す傾向があり、人口構成の変化が貯蓄率を押し下げる
3.若年層の消費性向の変化
若年層の消費意欲の高まりと「今を楽しむ」価値観の定着
4.社会保障負担の増加
年金・医療保険料等の負担増加により可処分所得が減少
特に注目すべきは世代間格差でしょう。
20代、30代の貯蓄率は1.5%程度にとどまり、40代でも2.8%と全世代平均を下回っています。一方で50代以上は4.5%と比較的高い水準を維持しています(金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」2023年)。
金融資産の構成比較:「現金・預金大好き」日本人の実態
日本人の金融資産構成は他国と比較するとかなり特徴的で、この傾向は長期にわたって続いています。
家計金融資産構成の国際比較(2023年)
| 資産種類 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | カナダ | 北欧諸国 |
| 現金・預金 | 53.8% | 13.5% | 26.2% | 39.5% | 32.3% | 21.8% | 18.9% |
| 債券 | 1.3% | 5.3% | 1.2% | 2.0% | 1.0% | 1.7% | 1.1% |
| 投資信託 | 4.5% | 11.2% | 3.6% | 12.5% | 7.2% | 15.5% | 10.2% |
| 株式等 | 10.5% | 36.5% | 12.8% | 18.0% | 26.5% | 32.0% | 25.4% |
| 保険・年金 | 27.5% | 31.5% | 53.2% | 28.0% | 31.0% | 27.0% | 42.5% |
| その他 | 2.4% | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
【データ出典:日本銀行「資金循環の日米欧比較」(2024)、OECD「Household Financial Assets」(2023)】
現金・預金偏重がもたらす長期的影響
日本人の現金・預金偏重が資産形成に与える影響を具体的な数字で見てみましょう。
100万円を20年間運用した場合の最終金額シミュレーション
- 全額預金(金利0.01%):100.2万円(+0.2万円)
- 米国平均的資産配分(年平均リターン5%):265.3万円(+165.3万円)
- 北欧平均的資産配分(年平均リターン4%):219.1万円(+119.1万円)
【シミュレーション前提:複利計算、税金・手数料等は考慮せず】
日本人の現金・預金選好の主な理由(金融庁調査2023年)
- 安全性を重視:68.5%
- 元本保証への強いこだわり:62.3%
- 投資への知識不足:53.2%
- 損失への恐怖心:47.8%
- 預金以外の選択肢の認知不足:35.6%
特に興味深いのは、日本人の「元本割れ許容度」の低さです。
「投資において元本の何%までの損失なら許容できるか」という調査では、日本人の平均回答は「5%まで」でした。一方、米国では「20%まで」、ドイツでは「15%まで」という結果でした(金融広報中央委員会「金融リテラシー調査」2022年)。
みなさまはどのくらいまで許容できますか?
金融リテラシーの国際比較:教育と環境の違い
残念ながら、金融知識やスキルを測る「金融リテラシー」スコアの国際比較でも、日本は決して高くありません。これは私たち社会人は学生時代に金融の勉強をしてこなかったことも要因でしょう。
OECD金融リテラシースコア(満点21点、2020年調査)
- 日本:12.1点
- OECD平均:13.0点
- 香港:14.8点(最高)
- オーストラリア:14.0点
- カナダ:13.9点
- ドイツ:13.9点
- 韓国:13.0点
- 英国:12.7点
- フランス:12.5点
- 米国:12.1点
- イタリア:11.1点
【データ出典:金融広報中央委員会「金融リテラシー調査」(2022)】
分野別の日本人の弱み(5点満点)
- 金融知識:3.5点(OECD平均3.9点)
- 金融行動:5.3点(OECD平均5.4点)
- 金融態度:3.3点(OECD平均3.7点)
特に低スコアだった具体的な質問項目:
- 複利計算の理解:正答率45%(OECD平均65%)
- インフレと購買力の関係:正答率61%(OECD平均82%)
- リスク分散の基本原則:正答率52%(OECD平均73%)
学校教育における金融教育時間の国際比較(年間時間)
- 米国:平均38時間
- 英国:平均28時間
- オーストラリア:平均25時間
- 日本:平均7時間
【データ出典:文部科学省「諸外国の教育事情調査」(2022)、金融経済教育推進会議報告書(2023)】
米国では小学校から投資の基礎や予算管理を学ぶのに対し、日本では高校でようやく限定的な金融教育が始まるという大きな差があります。
また、家庭内での金融教育も米国では6割以上の家庭で行われていますが、日本では2割程度にとどまります。
投資行動の特徴:リスク回避傾向が強い日本人
投資に関する国際調査によると、日本人投資家には以下の特徴があります。
株式・投資信託等の保有率(2023年)
- 日本:31.2%
- アメリカ:52.3%
- イギリス:33.7%
- ドイツ:40.1%
- フランス:36.4%
- カナダ:48.9%
- オーストラリア:41.2%
【データ出典:ブラックロック「グローバル投資家調査」(2023)】
各国の投資家心理比較
「リスクを取りたくない」と回答した割合
- 日本:75.2%
- アメリカ:43.1%
- ドイツ:58.4%
- シンガポール:39.7%
- 中国:35.2%
「短期的な値動きが気になる」と回答した割合
- 日本:82.3%
- アメリカ:48.5%
- ドイツ:52.7%
- 韓国:58.2%
「長期投資(10年以上)を行っている」と回答した割合:
- 日本:12.7%
- アメリカ:41.5%
- カナダ:39.3%
- ドイツ:28.5%
【データ出典:野村総合研究所「証券投資に関する国際比較調査」(2023)】
投資行動の日米比較(個人投資家対象、2022年)
| 投資行動 | 日本 | アメリカ |
| 平均保有銘柄数 | 3.7銘柄 | 8.2銘柄 |
| 平均投資期間 | 2.3年 | 7.5年 |
| 定期的な積立投資実施率 | 28.5% | 68.3% |
| 初めての投資年齢(平均) | 39.8歳 | 27.3歳 |
| 投資情報収集時間(週平均) | 1.2時間 | 3.5時間 |
【データ出典:JPモルガン・アセット・マネジメント「投資行動調査」(2023)】
日本人投資家の課題
こうしたデータから、日本人投資家特有の課題が見えてきます!
- 投資開始年齢が遅く、複利効果を十分に活用できていない
- 分散投資の不足による個別リスクの高さ
- 短期的視点での売買による長期リターンの逸失
- 投資教育不足による意思決定の質の低下
米国では投資が「資産形成の手段」として一般的である一方、日本では依然として「投機・ギャンブル」というイメージが根強く残っています。
退職後の資金準備:老後に対する意識と現実
じつは、退職後の資金準備に関する国際比較でも興味深い結果が出ています。
「退職後の資金が十分にある」と回答した割合(2023年)
- 日本:18%
- グローバル平均:28%
- インド:50%(最高)
- 中国:47%
- オーストラリア:32%
- 米国:31%
- 英国:26%
- ドイツ:22%
- 韓国:20%
- フランス:12%(最低)
【データ出典:エーゴン「退職準備指数」(2023)】
退職後に必要と考える年間生活費(現役時代の年収に対する比率)
- 日本:61%
- アメリカ:78%
- ドイツ:75%
- フランス:72%
- 英国:68%
- シンガポール:73%
【データ出典:フィデリティ・インターナショナル「グローバル・リタイアメント調査」(2023)】
日本人は「老後は質素に暮らす」という前提を持つ傾向がありますが、実際の老後生活の質を考えると、より現実的な資金計画が必要です。
退職準備のための月々の貯蓄・投資額(可処分所得に対する比率)
- 日本:8.5%
- アメリカ:12.3%
- カナダ:11.8%
- ドイツ:10.2%
- オーストラリア:13.5%
- シンガポール:15.7%
【データ出典:HSBC「グローバル退職調査」(2023)】
公的年金への依存度(退職後収入の予想構成比)
- 日本:62.5%
- アメリカ:38.2%
- ドイツ:45.3%
- 英国:42.7%
- スウェーデン:47.2%
- オーストラリア:40.1%
【データ出典:OECD「Pensions at a Glance」(2023)】
日本人の公的年金への依存度の高さは、私的年金や個人の資産形成の重要性がまだ十分に認識されていないことを示唆しています。実際、厚生労働省の調査によれば、平均的な老後資金不足額は2,000万円程度と言われているのはみなさまご存知かもしれません。
世代別・職業別の国際比較:日本の特徴
世代別の資産形成状況の日米比較(30代、中央値)
| 項目 | 日本 | アメリカ |
| 金融資産保有額 | 450万円 | 820万円 |
| 年収に対する金融資産比率 | 0.8倍 | 1.2倍 |
| 株式等リスク資産比率 | 15.2% | 52.3% |
| 持ち家比率 | 35.2% | 42.5% |
| 老後資金の準備開始年齢 | 34.5歳 | 27.8歳 |
【データ出典:野村総合研究所「日米家計調査」(2023)】
職業別の投資行動比較(日本国内、2023年)
| 職業 | 投資実施率 | リスク資産比率 | 月間投資額(平均) |
| 公務員 | 32.5% | 18.3% | 2.8万円 |
| 会社員(大企業) | 38.7% | 22.5% | 3.5万円 |
| 会社員(中小企業) | 25.2% | 16.2% | 2.2万円 |
| 自営業 | 35.8% | 24.3% | 4.1万円 |
| 医療従事者 | 45.2% | 28.5% | 5.6万円 |
| IT関連職 | 53.1% | 35.2% | 6.8万円 |
【データ出典:金融広報中央委員会「職業別金融行動調査」(2023)】
特にIT関連職の投資実施率・投資額の高さが目立ちます。この傾向は米国でも同様で、情報へのアクセスのしやすさや国際的な視点を持つ機会の多さが影響していると考えられます。
FPからのアドバイス:日本人が見直すべき5つのポイント
国際比較から見えてきた日本人の特徴を踏まえ、私からのアドバイスをお伝えします。
リスク資産への適切な資産配分
超低金利が続く日本では、預金だけでは資産形成が難しい状況です。国際分散投資を含めたポートフォリオの構築が重要です。
具体的アクション例:
- 年齢を100から引いた数字を目安にリスク資産比率を設定(例:30歳なら70%)
- 投資初心者は全世界株式インデックスから始める
- 毎月の収入の最低10%を長期投資に回す習慣をつける
長期・積立・分散投資の徹底
日本人に特に不足している「長期投資の視点」を持つことが重要です。
具体的アクション例:
- iDeCoやつみたてNISAを最大限活用(税制優遇で利回り向上)
- 「投資は5年以上」という意識を持ち、短期的な値動きに一喜一憂しない
- 価格が下がった時こそ買い増しのチャンスと捉える発想の転換
早期開始の重要性を認識
複利の力を最大限活用するためには、投資開始年齢を前倒しすることが効果的です。
複利効果の比較: 月3万円を年利4%で運用した場合の最終金額
- 25歳~65歳(40年間):約3,600万円
- 35歳~65歳(30年間):約2,300万円
- 45歳~65歳(20年間):約1,300万円
10年の差が最終的な資産額に大きな影響を与えることが分かります。
金融リテラシーの継続的な向上
投資の基礎知識、複利の力、リスク分散の考え方など、基本的な金融教育を受けることで、より良い選択ができるようになります。
具体的アクション例:
- 金融庁や日本証券業協会の無料セミナーを活用
- 信頼できる情報源(書籍・ウェブサイト)から継続的に学ぶ
- 投資仲間を作り、知識や経験を共有する
老後資金計画の見直し
公的年金だけに頼らない、自立した老後生活のための資金計画が重要です。
具体的アクション例:
- 老後必要資金を具体的に計算(平均的に夫婦で2,500万円~3,000万円が目安)
- 公的年金シミュレーションで自分の受給予想額を確認
- 不足分を私的年金や投資で補う具体的な計画を立てる
まとめ
国際比較のデータから見えてくる日本人の家計事情について、興味深いポイントをまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
国際比較から見ると、日本人の「現金・預金志向」「リスク回避傾向」「金融リテラシーの低さ」「短期的視点」「老後資金計画の甘さ」という特徴が浮かび上がります。しかし、これらは決して変えられないものではありません。
近年、日本でも投資信託の保有世帯は徐々に増加しており、特に20代・30代の若年層を中心に投資への関心が高まっています。つみたてNISAの口座開設数は2023年末時点で800万口座を超え、iDeCoの加入者も増加傾向にあります。
適切な知識を身につけ、自分に合った資産形成を行うことで、将来の安心を手に入れることができます。国際比較から学び、日本人の弱点を克服することが、より豊かな人生を送るための第一歩となるでしょう。