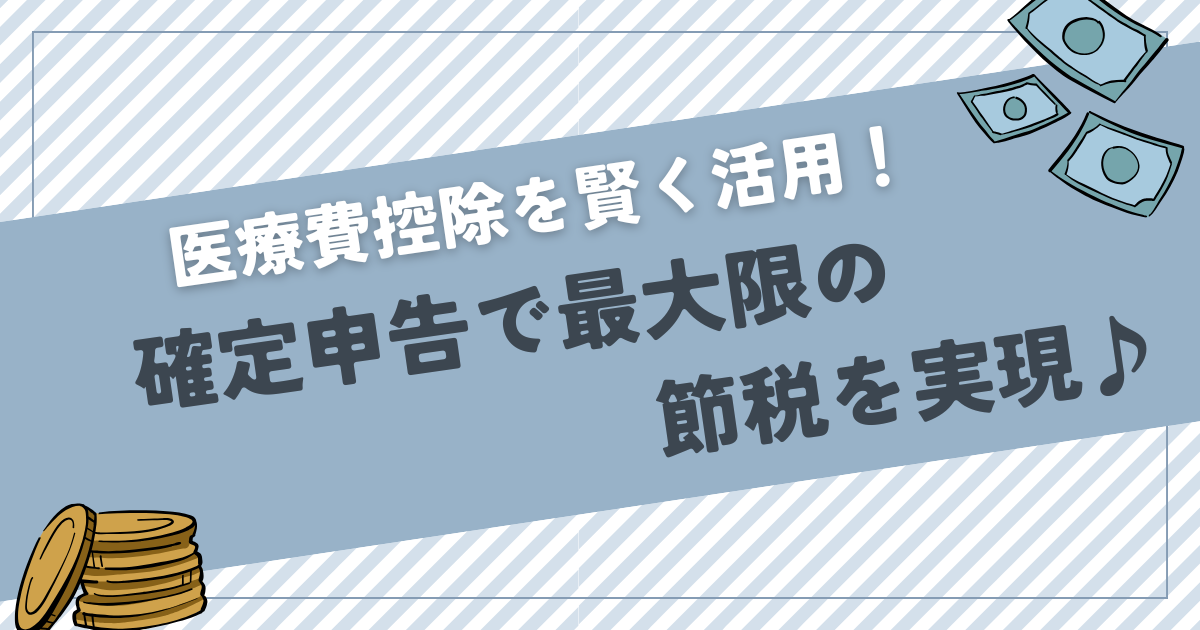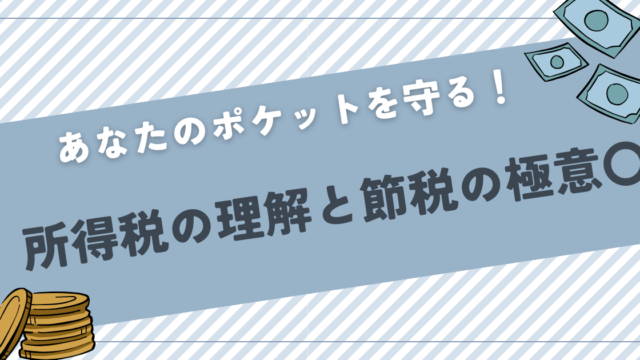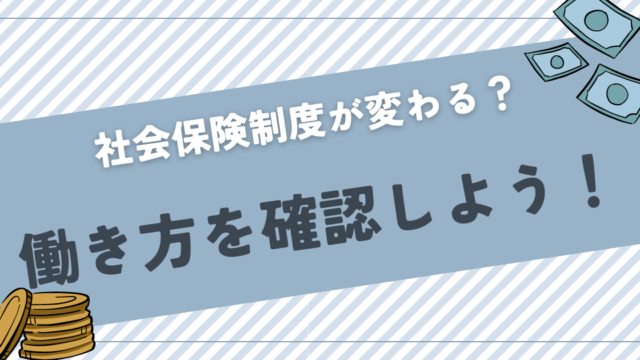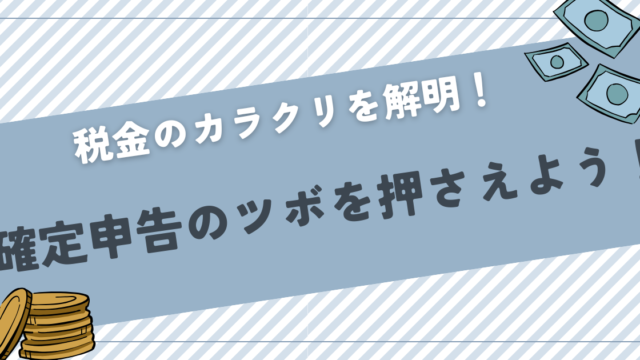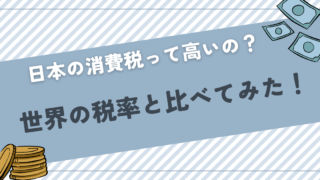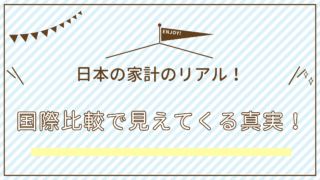みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
毎年の確定申告は多くの方にとって大変な作業ですが、医療費控除を活用することで節税が可能です。
特に、医療費が高額になった年には大きなメリットがあります!!
今回は、医療費控除の基本から具体的な申請方法までをわかりやすく解説し、節税効果を最大限に引き出す方法をご紹介いたします♪
医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた部分を所得税から控除できる制度です。
医療費控除の対象となる医療費には以下のようなものがあるのでキソとして知っておくとよいでしょう(*’▽’)
診察費用: 医師の診察料や治療費
入院費用: 病院やクリニックでの入院費用
薬代: 処方された薬の費用
歯科治療費: 虫歯の治療などの歯科治療費用
交通費: 通院にかかる公共交通機関の費用(タクシー代は特例を除き対象外)
特定の治療用サプリメント: 医師の指示で購入した治療用サプリメントや医療器具
また医療費控除を活用するための条件もあります。
自分自身が条件を満たしているのかどうかは毎年確認をしていきましょう!
・総所得金額の5%または10万円(どちらか低い方)を超える医療費が対象。
・自分や生計を共にする配偶者、扶養親族の医療費が対象。
例えば、年間の総所得金額が400万円の場合、10万円を超える医療費が医療費控除の対象となります。
医療費控除の申請方法

医療費控除を申請するには、確定申告書に必要な情報を記入し、税務署に提出する必要があります。
何もしなくてもよいわけではありません。対象の方は申請をしてくださいね!
必要書類としては、医療費の領収書や明細書があげられます。
面倒かもしれませんが、医療機関から受け取った領収書を保管しておきましょう。
手続きについて
①
確定申告書AまたはBを用意する。(Aは給与所得者用、Bは自営業者や複数の所得がある人用)
医療費控除の明細書を記入し、医療費の総額を計算する。
確定申告書に医療費控除の金額を記入する。
必要書類を添付して税務署に提出する。
②
e-taxから申告を行う。
確定申告の提出期間は決まっています。ご存知の方も多いかと思いますが、例年2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)です。この期間内に申請を行う必要があります。
医療費控除の計算方法
医療費控除額は、以下の計算式で求めることができます。
医療費控除額=
実際に支払った医療費−保険金等で補填される金額
−max(10万円,総所得金額×0.05)
ご自身がお支払いになった医療費がいくらなのか、まずは確認をするとよいでしょう。
医療費控除のポイント

医療費控除の対象となる医療費は多岐にわたりますが、見逃しやすい項目もあります。
例えば、通院にかかる交通費(公共交通機関の利用に限る)や予防接種費用も対象となります!!
また、治療目的で購入したサプリメントや健康食品も場合によっては対象となることがあります。
医療費控除を申請する際には、以下の点に注意しましょう(*’▽’)
・保険金等で補填された金額は控除対象外
・領収書や明細書は必ず保管しておきましょう
(税務署からの確認が入ることがある可能性も)
・予防接種や美容整形などの医療費は控除対象外となる場合がある
医療費控除を活用した節税のメリット
医療費控除を適用することで、所得税と住民税の負担が軽減されます。
医療費で使ったとはいえど、しっかりと節税効果があります。
その節税効果については、その方の課税所得に対する税率によって変わってくるので気になる方は確認してみるとよいでしょう。
また、医療費控除を活用することで、高額な医療費が発生した年に税負担を軽減し、将来の医療費に備えることができます。
これにより、家計の安定を図ることができます。
まとめ

医療費控除の基本から具体的な申請方法、節税効果を最大限に引き出す方法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
医療費控除は、多くの方が見落としがちな節税ポイントですが、上手に活用することで税金の負担を大幅に軽減することができます。
特に、高額な医療費が発生した年には積極的に申請することをおすすめします。
確定申告の際には、医療費控除の適用範囲を確認し、自分自身の申請に役立ててください。
税理士や専門家に相談することで、より効果的な節税対策を実現しましょう。